【物流2024年問題】運送業界のM&Aとは|最新動向・売却相場・事例・メリット/デメリットを解説

本記事では、運送業界のM&Aの最新動向を解説しています。
メリット・デメリット、売却相場の考え方、近年の事例、コロナ後や2024年問題の影響、案件の探し方まで整理しています。
EC市場の拡大や2024年問題を背景として、大手企業を含めて、運送業界でのM&Aが活発に行われています。
一方で、燃料費の高騰などを背景に中小の運送会社では利益率が低下し、苦しい経営状況が続いているのも事実です。
運送業界では今後も慢性的なトラックドライバー不足やEC市場の更なる拡大による需要増加が見込まれているため、中長期的な成長を実現するための経営戦略が必要です。
運送業のM&A・事業承継を検討している経営者の方はぜひ、参考にしてください。
M&Aナビには、様々な企業規模や業種の売り手・買い手の方にご登録をいただいており様々な出会いのお手伝いをしています。
中でも運送業界のお客様からご相談いただくことが多く、支援実績が豊富にございます。
運送業界でM&Aを考えられている方でお困りごとやお悩み事がある方はお気軽にご相談ください。
目次
- 1 運送業界の動向(市場・参入・人手不足・テクノロジー)
- 2 運送業界のM&Aのメリット(売り手・買い手)
- 3 運送業界のM&Aのデメリット(売り手・買い手)
- 4 運送業界の売却相場(評価の考え方・業界特有ポイント)
- 5 運送業界のM&A事例 19選(近年のトピック)
- 5.1 アート引越センターによるヤマトホームコンビニエンス株式会社の完全子会社化
- 5.2 SBSホールディングスによるNSKロジスティックス株式会社の株式取得
- 5.3 セイノーホールディングスによる三菱電機ロジスティクスの株式取得
- 5.4 センコーによる株式会社オプラスの子会社化
- 5.5 東部ネットワークによるテーエス運輸の子会社化
- 5.6 エスライングループによる拓進物流の傘下入り
- 5.7 エスライングループによるエムアンドエスコーポレーションの子会社化
- 5.8 セイノーホールディングスによる日祐株式会社のグループ入り
- 5.9 トナミホールディングスによる株式会社アペックスの完全子会社化
- 5.10 トナミホールディングスによる山昭運輸株式会社の子会社化
- 5.11 トナミホールディングスによる山一運輸倉庫株式会社の子会社化
- 5.12 トナミホールディングスによる丸嶋運送株式会社の子会社化
- 5.13 ゼロによる株式会社ソウイングの子会社化
- 5.14 LDEC(ロジスティード子会社)によるアルプス物流への公開買付結果に関するお知らせ
- 5.15 東部ネットワークによるテーエス運輸株式会社の子会社化
- 5.16 セイノースーパーエクスプレスによる関東エアーカーゴ株式会社の航空部門の吸収分割
- 5.17 トナミによるケーワイケーの買収
- 5.18 ゼロによるHIZロジスティクスの買収
- 6 運送業界の平均利益率とキャッシュフロー
- 7 コロナ後の運送業界M&A動向(評価される会社・人材/車両・ガバナンス)
- 8 運送業のM&A案件を探すには(3つの手段)
- 9 まとめ
運送業界の動向(市場・参入・人手不足・テクノロジー)

運送業界は、市場規模約39兆円の一大産業です。その内訳は「旅客運送14兆円」と「物流25兆円」であり、物流の比率が高くなっています。(※1)
物流は、トラックや船、航空機などのさまざまな交通手段を用いて、製品を生産者から消費者に引き渡すものです。
その中で、もっとも大きな割合を占めるのはトラック運送業の約60%であり、物流業界ひいては運送業界の動向に強い影響を及ぼしていることが分かります。
こちらでは、トラック運送業の動向を見ていくことで運送業界全体の動向を探っていきたいと思います。
市場動向

トラック運送業は、平成2年の物流二法の施行によって参入事業者数が爆発的に増えたことで知られていますが、昨今のECの進展によってさらに競争が激化してきています。
EC業者の販売戦略である「送料無料」や「全国一律料金」などが打ち立てられ、消費者にとっては気軽にオンラインで買い物ができる時代が訪れました。
そのことがトラック運送業の市場にも強く影響を及ぼし、営業収入15兆円前後で推移するようになりました。
(※2)ECの進展は、運送会社の送料負担という問題を抱えてはいますが、運送業界全体としては今後も高い水準で推移していくと見られています。
新規参入の多さ
トラック運送業の新規参入数は、物流二法の施行当時と比較すると落ち着きを見せています。しかし、昨今の競争激化においても毎年約1,000者が新規参入を果たしています。(※2)
その背景にあるのは、前述したECの進展や新規参入の敷居の低さです。
ECの進展によるトラック運送業の需要増加が見込まれている現状で、シェアを獲得しようと乗り出してきています。
また、事業に要する物が一定数の車両で良いという特徴から、比較的少ない資本で新規参入できる業界であることも強く影響していると考えられます。
車両に関しては、リースやローンを活用することができれば多額の資金を準備するよりも先に事業の立ち上げも可能だといえるでしょう。
トラックのリースやローンに関しては以下のメディアも参考にしてみてください。
トラックリース&ローンドットコム
トラックドライバー不足の深刻化

日本の少子高齢化に伴い、あらゆる業種において労働力の確保が課題になっています。
中でも、運送業のトラックドライバー不足は深刻です。一般的な業種と比較して低賃金・長時間労働という特徴から、若年層から敬遠されてしまっている問題があります。(※2)
これを受けて、平成30年12月には「貨物自動車運送事業法」が改正されました。規制の適正化や荷主対策の深度化などが盛り込まれた内容となっており、全日本トラック協会や各機関との連携により、トラックドライバーの労働条件の改善を目指していくとされています。
テクノロジーの進化

さまざまな業界でIoTやAIの導入が進んでいますが、運送業界も大きな影響を受けています。
トラック運送業でもっとも期待されているのは、トラックの自動運転化です。
米国では既に一部商業運用もされており、日本においても平成30年に北関東道でトラック隊列走行の実証がおこなわれました。(※3)
現段階のテクノロジーだと完全自動は難しく、トラックドライバーの搭乗が必須とされています。しかし、将来的には完全無人化を目指すとしており、実現すればトラックドライバー不足の解消と人件費の大幅な削減が叶います。
自動運転が確立されれば、トラック運送業だけでなく運送業界全体で技術革新が進むことが期待されています。
トヨタやホンダなどの大手の会社を始め、立ち上げて間もないスタートアップも積極的な取り組みを見せています。
運送業界の動向については、以下のメディアも参考にしてみてください。
運送・物流業界向けオンラインマガジン|トラッカーズマガジン
運送業界のM&Aのメリット(売り手・買い手)
近年、運送業界では大手企業グループも含めて多くのM&Aが実施されています。
ではM&Aの当事者となっている売り手や買い手の企業にはM&Aを行った結果、どういうメリットがあるのでしょうか。
この章では、売り手と買い手の双方の視点から運送業界のM&Aのメリットについて解説します。
売り手のメリット
運送業界におけるM&Aでは、特に売り手にとって多くのメリットがあります。ここでは、後継者不在の問題解決、従業員の待遇改善、コスト削減という三つの主要なメリットに焦点を当てて解説します。
後継者不在問題の解決
多くの運送業者は家族経営が一般的であり、創業者が退職または他界する際に後継者が不在という問題が発生しやすいです。M&Aにより、他の企業が事業を引き継ぐことで、このような後継者問題をスムーズに解決することが可能になります。これにより、企業の持続性が保たれ、従業員の雇用も維持されるため、地域社会にとってもプラスの影響があります。
従業員の待遇改善
M&Aによる規模の拡大や経営資源の統合は、従業員の待遇改善にも寄与します。特に資本力のある企業との合併は、従業員に対する給与の増加、福利厚生の充実、キャリアアップの機会など、より良い労働条件を提供することが可能です。これにより、従業員のモチベーションの向上や離職率の低下が期待できます。
コスト削減
M&Aを活用することで、運送業界におけるコスト削減が達成可能です。具体的には、車両の統合、保険料の共同購入、管理部門の統合による人件費削減などが挙げられます。これらのコスト削減は、企業の収益性の向上に直結し、競争力のある価格設定が可能になるため、市場での優位性を確保する助けとなります。
このように、運送業界におけるM&Aは売り手にとって非常に魅力的な選択肢であると言えます。続いて、買い手のメリットについて詳しく見ていきましょう。
買い手のメリット
運送業界におけるM&Aは買い手にも大きなメリットをもたらします。ここでは、事業エリアの拡大、集配拠点の増加、ドライバーやトラックの獲得、そしてスケールメリットを実現することについて詳述します。
事業エリアの拡大
運送業界では地理的なカバー範囲が事業の成功に直結します。M&Aにより他の運送会社を取得することで、買い手は新たな地域市場へのアクセスを獲得し、その結果、全国または国際的な配送ネットワークを拡張することができます。これにより、より広範な顧客基盤を築き、業務の多様化と収益の増加が見込めます。
集配拠点の増加
集配拠点は運送業の効率を大幅に向上させるために重要です。M&Aを通じて他の企業の集配拠点を獲得することで、買い手は物流の効率化を図り、配送時間の短縮やコスト削減を実現できます。特に大規模な物流を要する企業にとって、これは大きな競争力の源泉となります。
ドライバー・トラックの獲得
運送業界では、ドライバーや車両の確保が常に課題となっています。M&Aを利用して他の運送企業の資源を取り込むことで、買い手は即座にこれらの貴重な資源を手に入れることが可能となり、サービスの拡大や運送能力の向上が期待できます。
スケールメリット
大規模な運送業者としての地位を確立することで、スケールメリットが生まれます。これには、購買力の向上、交渉力の強化、そして市場における影響力の増大が含まれます。これらのメリットは、さらなる事業拡大や新規市場への進出を容易にし、長期的な成長戦略を支える重要な要素となります。
以上のように、運送業界でのM&Aは買い手にとっても多くの利点をもたらし、事業拡大と効率化の大きな機会を提供します。
運送業界に限らず、M&Aは多くのメリットをもたらします。
M&Aのメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

M&Aのメリットとは?売手・買手の視点からわ...
M&Aは、買手側はもちろんのこと売手側にも大きなメリットをもたらします。 特に、近年の中小企業では、後継者不在の解決先の有効的な手段としてM&Aを活用することが活発になってきました。 この記事では、売…
運送業界のM&Aのデメリット(売り手・買い手)
前章にて、運送業界のM&Aにおける売り手と買い手の双方の立場からのメリットについて解説をしました。
運送業界のM&Aにおいては、多くのメリットがある一方でデメリットが存在することも事実です。
この章では、運送業界のM&Aにおける売り手と買い手の双方の立場のデメリットについて解説します。
売り手のデメリット
運送業界におけるM&Aは多くのメリットがありますが、売り手にとってはいくつかのデメリットも存在します。主な問題点は、希望条件に届かない可能性、競業避止義務の課せられること、そして取引先との関係性悪化のリスクです。
それぞれ解説をしていきます。
希望条件に届かない可能性がある
売却時に売り手が期待している条件と実際に提示される条件が一致しないことは珍しくありません。市場の需給バランス、業界内の競争状況、企業の財務状態など、多くの外部要因により評価額が影響を受けるためです。これにより、売り手が満足する取引が実現しない可能性があります。
競業避止義務が課される
M&A取引において、多くの場合に売り手は競業避止義務を課されます。これは、売り手が一定期間、同じ業界内で新たなビジネスを開始したり、既存の事業と競合する行動を取ることを制限されるというものです。
これにより、売り手の将来のビジネス機会が制限されることになります。
特に運送業では営業エリアが広範囲に広がっているため同じビジネスを立ち上げることは難しいと考えてよいでしょう。
取引先との関係性悪化のリスクがある
運送業界は顧客との密接な関係が成功の鍵です。M&Aを通じて会社が売却されると、取引先が変更に不満を持つことがあり、これまで築いてきた信頼関係が損なわれる可能性があります。特に、サービスの質が変わると感じられた場合、顧客が他の運送会社へ移行するリスクがあります。
買い手のデメリット
一方、買い手にもいくつかのデメリットが存在します。これには、簿外債務の承継リスクと管理コストの増加が含まれます。
簿外債務の承継リスクがある
買い手は、M&Aによって買収する企業の隠れた負債や簿外債務を引き継ぐリスクを負います。これらの負債が事前のデューデリジェンスで明らかにならない場合、後から大きな財務的負担が発生することがあります。
簿外債務については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

簿外債務とは?M&Aにおける問題点や対応策を...
会社を売却する際に問題となることがある簿外債務ということばを聞いたことはありますか? 簿外債務とは、貸借対照表に計上されない負債のことをいいます。 簿外債務の影響で、買手と問題になり、最悪の場合は訴訟に繋がる恐れもありま…
管理コストが増えるリスクがある
企業を統合する過程で、管理の複雑さが増すことが予想されます。これは、異なる企業文化の融合、従業員の統合管理、システムの統一など、多くの追加コストを発生させる可能性があります。この過程で生じる追加の管理コストは、統合の利益を相殺することもあります。
運送業界でのM&Aは、様々な機会を提供する一方で、これらのリスクを慎重に管理する必要があります。以上が、運送業界のM&Aのデメリットに関する主なポイントです。
運送業界の売却相場(評価の考え方・業界特有ポイント)
では、運送業界の会社が売却を検討する場合の相場はあるのでしょうか。この章では、運送業界における売却価格の考え方について解説します。
運送業の売却価格の考え方
運送業界における企業売却価格を決定する際には、複数の要因が考慮されます。主な要素としては、企業の財務状況、市場での競争力、運営資産の質、将来の成長見込みなどがあります。これらの要素を総合的に評価することで、適正な売却価格が算定されます。
売却価格を算出する一般的な方法には、収益ベースのアプローチ、資産ベースのアプローチ、市場ベースのアプローチがあります。収益ベースでは、将来のキャッシュフローを割引して現在価値を求める方法が一般的です。資産ベースでは、企業の資産と負債を精査し、純資産の価値を算定します。市場ベースでは、同業他社の売買事例や株価などを参考にします。
M&Aにおける企業価値の考え方については、以下の記事で詳細に解説しています。
ご興味ある方はぜひご連絡ください。

【事業売却の相場について解説】M&Aで会社売...
あなたが「会社を売りたい」と考えたとき、一体いくらで売るのが最適だと思いますか? M&Aにおいて「会社の価値(株価)を正しく算出する」ことは非常に重要です。 特に未上場企業の場合は株価が公開されているわけではあ…
運送業界特有のポイント
運送業界では、特有のポイントが売却価格に影響を与えることがあります。
例えば、運送免許の保有状況、運行ルートの専有性、クライアントとの長期契約の有無が重要な評価ポイントとなります。
また、運送業界は地域によって需要が異なるため、地理的な位置も重要なファクターです。
さらに、近年では環境規制への対応状況も価格評価に影響します。例えば、エコロジカルな車両への更新や、CO2排出量の削減に向けた取り組みが評価されることがあります。
M&Aを始めてみないとわからない
M&Aは多くの場合、事前にすべてのリスクや機会を完全に把握することは難しいです。
実際にプロセスを進める中で初めて明らかになる課題や、新たな機会が見えてくることがあります。
そのため、M&Aを進める際には柔軟な対応と継続的な評価が必要です。
このように、運送業界における企業売却は、多面的な評価が求められる複雑なプロセスです。
売却を検討している企業は、専門的なアドバイスを得ながら適切な準備を行うことが成功への鍵となります。
M&Aナビでは、運送業界の方からの売却のご相談を多数受けており、支援実績も豊富にあります。
まずは無料のご相談から!お気軽にお問い合わせください。
運送業界のM&A事例 19選(近年のトピック)
運送業界を取り巻く動向によってM&Aが活性化しています。こちらでは、運送業界のM&A事例を19個ピックアップしました。
アート引越センターによるヤマトホームコンビニエンス株式会社の完全子会社化
2024年8月、アート引越センター株式会社(以下「アート」)は、ヤマトホールディングス株式会社(以下「ヤマトHD」)が保有するヤマトホームコンビニエンス株式会社(以下「YHC」)の全発行済普通株式の49%を取得し、アートグループの完全子会社化することに合意しました。
アートは、引越業界で高い評価を受けるリーディングカンパニーであり、より良い暮らし方の提案を目指して事業領域を拡大しています。
今回のM&Aの目的は、大型家財の配送事業と引越事業のシナジーをさらに強化し、アートグループのさらなる成長を目指すことです。
参照:アートグループによるヤマトホームコンビニエンス株式会社の完全子会社化のお知らせ
SBSホールディングスによるNSKロジスティックス株式会社の株式取得
2024年10月、SBSホールディングス株式会社(以下「SBSHD」)は、日本精工株式会社(以下「NSK」)が所有するNSKロジスティックス株式会社(以下「NLK」)の発行済株式の66.61%を取得し、合弁会社として新たに「SBS NSKロジスティクス株式会社」が設立されました。
NSKは、国内物流の持続性と効率化を追求し、SBSHDのノウハウとリソースを活用し、物流機能の高度化と成長を目指しています。
今回のM&Aの目的は、物流機能の持続可能性を確保し、環境対応や効率化に向けた取り組みを強化することです。
参照:NSKグループ物流機能会社の一部株式の譲渡完了について
セイノーホールディングスによる三菱電機ロジスティクスの株式取得
2024年6月、セイノーホールディングス株式会社(以下「セイノーHD」)は、三菱電機株式会社(以下「三菱電機」)が保有する三菱電機ロジスティクス株式会社の普通株式の一部(66.6%)を取得するための株式譲渡契約を締結しました。
本取引により、三菱電機ロジスティクスは、三菱電機の子会社からセイノーHDの連結子会社に移行します。
セイノーHDは、このM&Aを通じて物流事業の強化を図り、三菱電機はセイノーHDの物流インフラを活用し、効率的なサプライチェーンの構築を目指します。
参照:三菱電機ロジスティクス株式会社の株式に係る株式譲渡契約書及び株主間契約書の締結並びに子会社の異動に関するお知らせ
センコーによる株式会社オプラスの子会社化
2024年5月、センコー株式会社(以下「センコー」)は、株式会社オプラス(以下「オプラス」)の全株式を取得し、同社をグループ化することを発表しました。
オプラスは、和歌山エリアを中心に食品や日用品の低温輸送を行う、地域トップクラスの物流会社です。
センコーは、このM&Aにより和歌山エリアの配送網を強化し、新規顧客の獲得を目指します。
オプラスは、センコーグループのノウハウを活用し、さらなる事業拡大を図る予定です。
参照:和歌山エリアの配送網を強化し、事業拡大を図る ~県内トップクラスを誇るオプラスを5月に子会社化~
東部ネットワークによるテーエス運輸の子会社化
2024年3月、東部ネットワーク株式会社(以下「東部ネットワーク」)は、テーエス運輸株式会社(以下「テーエス運輸」)の発行済株式の100%を日本エア・リキード合同会社から取得することを発表しました。
テーエス運輸は、液化酸素、液化窒素、液化アルゴンなどの産業用ガスの輸送を手掛けており、今後は水素など新エネルギーの輸送事業にも注力しています。
今回のM&Aの目的は、産業用ガス輸送事業の強化と新エネルギー輸送の拡大を図り、東部ネットワークグループのさらなる成長を目指すことです。
参照:テーエス運輸株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ
エスライングループによる拓進物流の傘下入り
2024年8月、株式会社拓進物流(以下「拓進物流」)は、株式会社エスライングループ本社の傘下に入り、エスライングループの一員として新体制のもとで再スタートを切ることを発表しました。
拓進物流は、より充実したサービスの提供を目指し、エスライングループの一員としてさらなる発展を図る予定です。
このM&Aの目的は、グループ全体のシナジー効果を活用し、物流事業の強化を目指すことです。
参照;組織体制変更のお知らせ
エスライングループによるエムアンドエスコーポレーションの子会社化
2023年9月、株式会社エスライングループ本社(以下「エスライングループ」)は、株式会社エムアンドエスコーポレーション(以下「対象会社」)の全株式を取得し、同社を子会社化することを決定しました。
エムアンドエスコーポレーションは関東エリアにおいて家電製品の配送や設置工事を行っており、エスライングループの既存のホームサービス事業とのシナジーを期待しています。
今回のM&Aの目的は、輸送網や事業基盤を組み入れることで、エスライングループの事業拡大と企業価値の向上を図ることです。
参照:「株式会社 エムアンドエスコーポレーション」の株式取得に関するお知らせ
セイノーホールディングスによる日祐株式会社のグループ入り
2024年4月、セイノーホールディングス株式会社(以下「セイノーHD」)は、日祐株式会社(以下「日祐」)の株式100%を取得し、同社をセイノーグループに迎えることを発表しました。
日祐は、神奈川県を中心にメール便の配送事業を行い、カタログ制作やDTP、印刷、メーリング加工、コールセンター運営なども展開しています。
今回のM&Aの目的は、首都圏における配布ネットワークの強化と、ラストワンマイル領域での社会課題解決や環境への貢献を図ることです。
参照:日祐株式会社のグループ入りに関するお知らせ 2024年04月01日
トナミホールディングスによる株式会社アペックスの完全子会社化
2024年6月、トナミホールディングス株式会社(以下「トナミHD」)は、民事再生手続中であった株式会社エーピー管財の新設分割によって設立された株式会社アペックスの全株式を取得し、完全子会社化することを発表しました。
エーピー管財の物流・倉庫事業を継承する新会社は、負債を引き継がず、事業資産と雇用を維持しながら事業規模の拡大を目指します。
今回のM&Aの目的は、物流業界における事業基盤の強化とトナミHDグループ全体の成長を促進することです。
参照:(開示事項の経過)株式会社アペックスの株式取得(完全子会社化)に関するお知らせ
トナミホールディングスによる山昭運輸株式会社の子会社化
2023年11月、トナミホールディングス株式会社(以下「トナミHD」)は、山昭運輸株式会社(以下「対象会社」)の全株式を取得し、同社を子会社化することを発表しました。
山昭運輸は、神奈川県横浜市を拠点に海上コンテナ輸送事業を展開しており、トナミHDの国際貨物輸送事業の強化に寄与すると期待されています。
今回のM&Aの目的は、物流ネットワークの拡大と経営資源の連携による企業価値向上を図ることです。
トナミホールディングスによる山一運輸倉庫株式会社の子会社化
2023年10月、トナミホールディングス株式会社(以下「トナミHD」)は、山一運輸倉庫株式会社(以下「対象会社」)の全株式を取得し、同社を子会社化することを発表しました。
山一運輸倉庫は静岡県富士市を拠点に、トラック輸送および倉庫事業を展開し、特に製紙関連の物流を取り扱っています。
今回のM&Aの目的は、静岡県を中心とした東名阪エリアでの拠点強化と、トナミグループ全体の物流提案力の向上、さらなる事業拡大を図ることです。
トナミホールディングスによる丸嶋運送株式会社の子会社化
2023年10月、トナミホールディングス株式会社(以下「トナミHD」)は、丸嶋運送株式会社(以下「対象会社」)の全株式を取得し、同社を子会社化することを発表しました。
丸嶋運送は、奈良県天理市を拠点にトラック輸送および倉庫事業を展開し、関西・関東圏へのスピーディーな配送が強みです。
今回のM&Aの目的は、関西エリアにおける拠点強化と、トナミグループ全体の物流提案力を向上させることです。
参照:「丸嶋運送株式会社」の株式取得に伴う連結子会社化のお知らせ
ゼロによる株式会社ソウイングの子会社化
2023年11月、株式会社ゼロ(以下「ゼロ」)は、株式会社ソウイングの全株式を取得し、同社を子会社化しました。
ソウイングは、栃木県小山市に本社を構え、車両輸送事業やオートオークション構内運営事業を展開しています。
今回のM&Aの目的は、輸送効率の向上とオートオークション事業のマーケットシェア拡大を図り、ゼログループ全体の企業価値を最大化することです。
参照:株式会社ソウイングの株式取得(子会社化)に関するお知らせ
LDEC(ロジスティード子会社)によるアルプス物流への公開買付結果に関するお知らせ
2024年10月4日、LDEC株式会社(以下「LDEC」)は、親会社であるロジスティード株式会社の一員として、株式会社アルプス物流(以下「アルプス物流」)の普通株式および新株予約権に対する公開買付けを終了しました。
本公開買付けは2024年8月22日に開始され、アルプス物流の16,328,000株の買付けが行われました。
今回のM&Aの目的は、ロジスティードグループ内にアルプス物流の事業基盤を取り込むことで、輸送効率の向上やマーケットシェア拡大を図り、グループ全体の企業価値を高めることです。
参照:株式会社アルプス物流(証券コード:9055)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
東部ネットワークによるテーエス運輸株式会社の子会社化
2024年4月、東部ネットワーク株式会社(以下「東部ネットワーク」)は、テーエス運輸株式会社(以下「テーエス運輸」)の全株式を日本エア・リキード合同会社から取得し、同社を子会社化することを発表しました。
テーエス運輸は、半世紀以上にわたり液化酸素や液化窒素、液化アルゴンの輸送を行っており、今後は新エネルギーである水素輸送にも力を入れています。
今回のM&Aの目的は、産業用資材および新エネルギーの輸送事業を強化し、東部ネットワークグループ全体の成長を加速させることです。
参照:テーエス運輸株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ
セイノースーパーエクスプレスによる関東エアーカーゴ株式会社の航空部門の吸収分割
2024年7月1日、セイノースーパーエクスプレス株式会社(以下「セイノースーパーエクスプレス」)は、関東エアーカーゴ株式会社(以下「関東エアーカーゴ」)の航空部門を吸収分割により承継することを発表しました。
セイノースーパーエクスプレスは、埼玉県および栃木県の一部地域での集配業務を担当し、EXPRESSネットワークの維持と品質向上を目指しています。
今回のM&Aの目的は、営業拡大と地域における管理強化により、お客様への価値提供を推進することです。
参照:セイノースーパーエクスプレスにおける吸収分割による事業継承について 2024年06月28日
トナミによるケーワイケーの買収

2018年4月、トナミHDは株式会社ケーワイケー(千葉県柏市)の全株式を取得して完全子会社化することを発表しました。
トナミHDは、富山県高岡市に本社を置く運送会社です。
中期経営計画において進められていた労働力確保や既存事業規模の拡大を図るため、今回のM&Aへと至りました。
ケーワイケーは、トラック運送業を中心に、倉庫保管管理業や流通加工業、3PL事業など幅広い事業を手掛けています。
ケーワイケーの労働力や事業エリアを獲得することでトナミグループ全体の事業力の底上げを図るとしています。
ゼロによるHIZロジスティクスの買収
2017年10月、ゼロは株式会社ロジスティクス(青森県八戸市)の全株式を取得して完全子会社化することを発表しました。
ゼロは、グループ全体の運送業の再編を進めており、地域別の統括会社を次々に設立させています。今回のM&Aも再編の一環でおこなわれたものと見られています。
HIZロジスティクスは、自動車の車両輸送を手がける運送会社です。今回のM&Aで「株式会社ゼロ・プラス東日本」に変更し、北海道・東北を管轄する役割を担うことになります。
全国5ブロック制を実現させたゼログループは、今後も会社の価値の創造や運送業の新たなビジネスモデルの確立を図っていくとしています。
運送業界以外も含まれますが、M&Aの成功事例34選をまとめた記事は以下からご確認ください。

M&A成功事例34選~大企業、中小企業、業界別...
この記事では、M&A(企業の合併・買収)が成功した34の事例を紹介します。 大企業や中小企業、業界別に分けて取り上げ、その成功の秘訣に迫ります。 中小企業においてもM&Aによる成長戦略の実現が一般化す…
運送業界の平均利益率とキャッシュフロー
運送業界が抱える大きな問題に「利益率の低さ」と「資金繰りの難しさ」があります。
こちらでは、運送業界の利益率が低い理由やキャッシュフローについて見ていきましょう。
運送業界の平均利益率
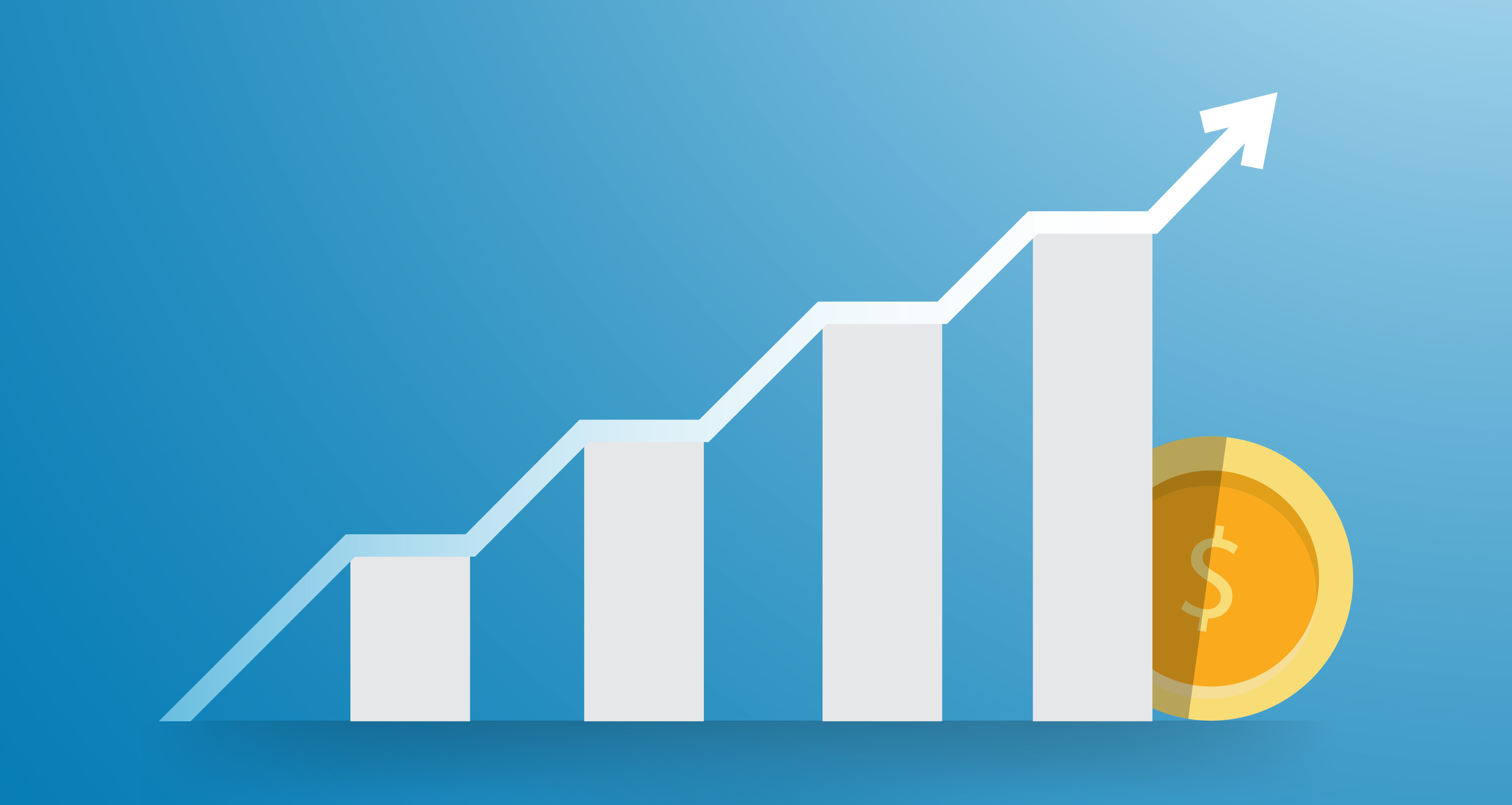
全日本トラック協会のデータによると、運送業の平均利益率は約1.0%というデータが明らかになっています。(※4)
営業赤字会社割合も減少しており、全体的に業績が改善されたといえるでしょう。
ただし、他の業種と比較すると依然として低い数値であり、今後も改善の余地があるといえるでしょう。
EC市場の拡大や燃料価格の下落など、好材料が揃いつつあるにも関わらず、平均利益率が改善されない理由は「トラックドライバー不足」にあると考えられています。
人材不足による人件費アップや傭車利用費の拡大により、事業にかけるコストが大幅に増加している現実があります。
運送業界のキャッシュフロー
キャッシュフローとは、お金の流れを意味する言葉です。運送業界の特性からキャッシュフローに悩む経営者は少なくありません。
運送業界の資金繰りが厳しくなる原因は、主に以下のものが挙げられます。
- 支払いサイトが長い
- 突発的な事故・故障の対応
- 基本的に費用が先払い
- 繁忙期の支払いが追いつかない
- 燃料費に大きく左右される
支払いサイトとは、代金の締日から支払日までの期間のことです。この期間中は売掛金を手にすることができないため、計画的に事業資金を運用しなければなりません。
問題は、運送業の支払いサイトが長いことです。一般的な業種は30日とすることが多い中、2ヶ月以上かかることも珍しくありません。この支払のズレが経営状態を悪化させていく原因となるケースが多く見受けられます。
また、繁忙期と閑散期の差が激しい問題もあります。特定期間にまとまった先出し費用を求められることで手元の事業資金が足りなくなる問題です。
業界全体が忙しくなるため、取引先からの突然の要請が頻発し、対応に追われてしまいます。
このような原因から運送業のキャッシュフローの悪化が進んでいます。経営者の努力で改善することが難しい問題も多く、経営者の悩みの種であると言えます。
売却検討中の方の疑問をいますぐ解決!よくある質問と回答はこちら

M&Aでよくある質問〜売却検討中の方の不安・...
M&Aで会社や事業の売却を検討する中で、不安や疑問点は多くあるのではないでしょうか。 M&Aナビにおいても「いくらで売れるのか知りたい」「売却後の税金が不安」といったご質問をいただいております。 そこ…
コロナ後の運送業界M&A動向(評価される会社・人材/車両・ガバナンス)

M&Aマーケットの総論として、コロナ前と比べると買手の意向はややシビアになってきています。M&Aナビを利用している買手のみなさまにおいても、以前よりは財務状態や経営計画の見通しについて厳しく判断される方が増えています。
それでは、コロナ禍における運送業界のM&A事情はどうなっているのでしょうか?
事業の基礎がしっかりできている運送会社は高い評価
ドライバー、トラック、顧客、そして拠点(センター)など、事業を継続的に運営していくにあたって必要となる資産をしっかり確保している運送会社は、コロナ禍においても非常に高く評価されており、すぐに高い価格で売れています。
運送会社を同業が買収する最も多い理由の一つが規模の拡大ですので、買収してすぐに事業の拡大が見込める会社は人気がでるのも頷けます。
赤字や借入があっても評価される場合あり

コロナ禍でも業績好調な運送会社は比較的多く、それらの会社は事業拡大のためにM&Aを積極的に検討しています。
M&Aで買収価格を決める際、一般的には純資産や利益を元に評価することが多く、赤字の会社や借入が多い会社は敬遠されがちです。
ところが運送会社の場合は、たとえ借入があってもドライバーやトラックをしっかり自社で保有していれば高く評価される一因となります。
それは、買手が既にもっている仕事や拠点を活用することで、早期に収益構造を改善しやすいことが理由です。
赤字企業を買収することのメリットについてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

M&Aで赤字企業を買収するメリットとは?節税...
「赤字の会社を買収する」というと、そのメリットを正確に答えることができる人は少ないでしょう。 まず、赤字企業と聞いてどのように想像されますでしょうか。 経営が不安定であると想像されがちですが、実はそうと言い切れないケース…
財務体質に加え「まっとうな会社」であることが最重要
M&Aマーケットにおいて、黒字であることや純資産が多いことが好まれることは言うまでもありません。しかしながら、高収益体質の会社を作り上げられる会社は一握りです。
しかし、まっとうな会社は経営者が努力すれば作ることが可能です。
たとえば、法令を遵守し適切な運航管理をしたり、ドライバーを正規待遇で雇用したりすることができていない運送会社は意外と多いものです。
今すぐ売却する気はなくても、外部の人に見られても恥ずかしくない内部管理体制を整えている会社にしておくことは、いざ売却するなり事業拡大するなりしたときに、間違いなくプラスに働きます。
会社売却の際によく話題にあがる簿外債務についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

簿外債務とは?M&Aにおける問題点や対応策を...
会社を売却する際に問題となることがある簿外債務ということばを聞いたことはありますか? 簿外債務とは、貸借対照表に計上されない負債のことをいいます。 簿外債務の影響で、買手と問題になり、最悪の場合は訴訟に繋がる恐れもありま…
運送業のM&A案件を探すには(3つの手段)
運送業のM&A案件を探すには、どのような手段があるのでしょうか。
一般的には、以下の3つの手段があります。
- M&Aマッチングサイトで探す
- 地元の金融機関に相談する
- M&A仲介会社に相談する
M&Aマッチングサイトで探す
M&Aマッチングサイトは、インターネット上で企業の売却案件を探すことができるサービスです。
特に近年ではM&Aの案件を探すための手段として主流になってきており活用する企業が増えています。
当社では、M&Aマッチングサイトを運営しており常時1,000件の売却案件を掲載しております。
運送業の案件もありますので、一度見てみてください。
地元の金融機関に相談する
地元の金融機関に相談することも有効な選択肢の一つといえます。
地方銀行や信用金庫は、地元企業の事業承継支援や経営支援に力を入れているためM&Aの売却案件の情報を保有している可能性が高いです。
一度、懇意にしている地域金融機関に相談してみましょう。
買収を検討しているエリアの金融機関に声をかけてみるのも有効な手段であるといえるでしょう。
M&A仲介会社に相談する
M&A仲介会社に相談することは、最もベーシックな手段の一つだといえるでしょう。
M&A仲介会社は、売却を検討している方を積極的に探索しており、売却案件の情報を豊富に持っていることが考えられます。
M&Aナビでは、プラットフォームに掲載していない非公開の案件を多数保有しておりますので、一度ご相談ください。
M&A仲介会社に相談する際は、手数料や費用など注意すべきことがいくつかあります。
詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。
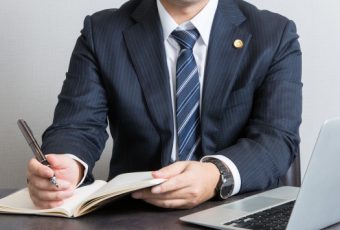
M&A仲介会社の選び方や費用について解説!2つ...
以前よりもM&Aが経営戦略の一つとして一般的になるにつれて、M&A仲介会社の選び方がポイントとなっています。 経済産業省も「中小M&A推進計画」を打ち出し、大企業だけでなく中小企業や小規模事業者におい…
まとめ
運送業界の動向や近年のM&A事例について見てきましたが、いかがでしょうか。
運送業界は市場規模が拡大する一方で、トラックドライバー不足や競争激化など、さまざまな問題を抱えているのも事実です。
その際の解決策としてM&Aを活用する経営者の方が増えています。現在、同じよう悩みを持たれている経営者の方はぜひ、売り手・買い手ともにM&Aにかかる手数料などを完全無料のM&Aナビをご利用ください。
また、他の業種の動向について気になる方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

【2025年最新】M&A業界の特徴と今後の動向!...
日本では後継者不在による黒字廃業が社会問題のひとつになっていることを背景にM&A業界の今後に注目が集まっています。 2025年までに70歳を超える中小・零細企業の経営者は約245万人と予想され、うち半数以上の約…

調剤薬局のM&Aを徹底解説!業界再編の状況や...
調剤薬局業界は、ここ数年もっとも活発にM&Aが行われ再編や統合が進んだ業界の一つだったといえるでしょう。 社会保障制度の見直しに伴う調剤費用の削減や薬剤師の不足、ドラッグストア業からの参入などにより、調剤薬局経…
(※1)国土交通省「物流を取り巻く現状について」
(※2)全日本トラック協会「日本のトラック 輸送産業 現状と課題」
(※3)国土交通省「トラック隊列走行の状況と課題」
(※4)全日本トラック協会「経営分析報告書」
経営分析報告書|公益社団法人全日本トラック協会

株式会社M&Aナビ 代表取締役社長。
大手ソフトウェアベンダー、M&Aナビの前身となるM&A仲介会社を経て2021年2月より現職。後継者不在による黒字廃業ゼロを目指し、全国の金融機関 を中心にM&A支援機関と提携しながら後継者不在問題の解決に取り組む。著書に『中小企業向け 会社を守る事業承継(アルク)』
関連記事

【法改正対応】未払い残業代がM&Aに与える影響とは?
会社を売却するときに残業代の未払いがあると大きな問題になりがちです。 会社を経営するにあたって、正しく残業代を支払うことは当たり前の義務ですが、M&A

会社売却後の従業員・社員・役員への影響は?買収されたら待遇はどうなる?
M&Aで会社売却をした後、いままで働いてくれていた従業員・社員にはどのような影響があるか不安に感じる経営者は多いのではないでしょうか。 従業員と長年の

M&Aの流れを徹底解説~会社を売却するための基礎知識~
M&Aは短い場合でも6カ月、長い場合は数年単位の取り組みになるため、その流れを理解しなければ希望条件を実現することは難しいでしょう。 M&A

M&Aによる会社売却を従業員・社員に公表する、ベストなタイミングとその方法とは?
M&Aによる会社売却を従業員や社員に公表することにより、信頼関係が崩れたり・不信感を持たれてしまうのでは? そんな不安を持たれている方も多いのではない
新着買収案件の情報を受けとる
M&Aナビによる厳選された買収案件をいち早くお届けいたします。





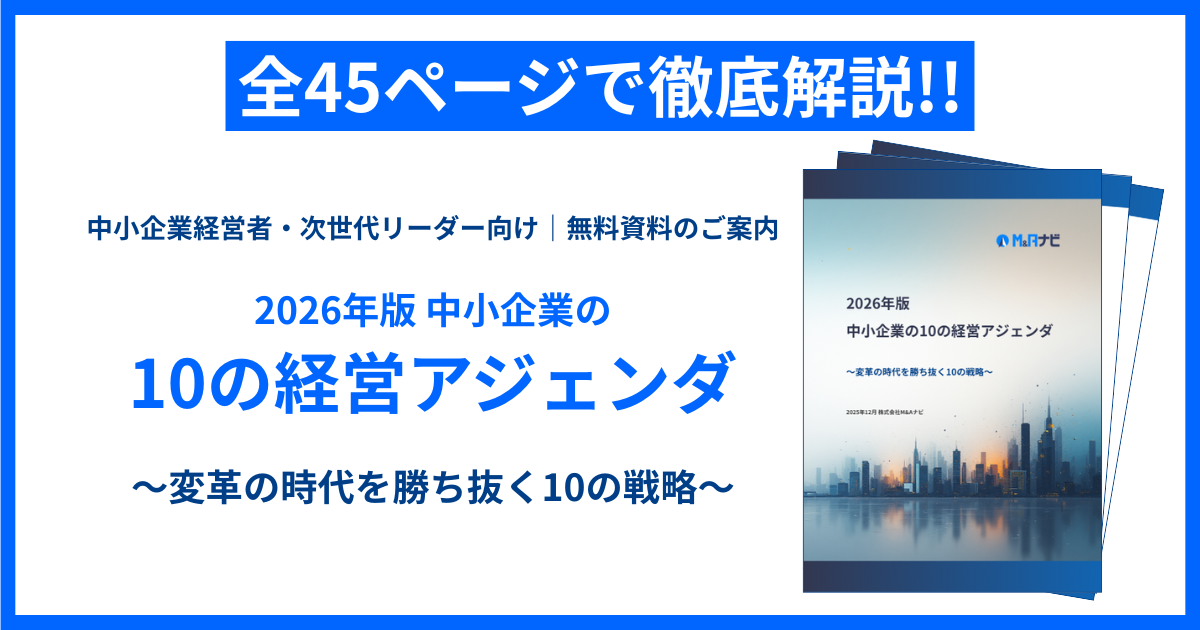

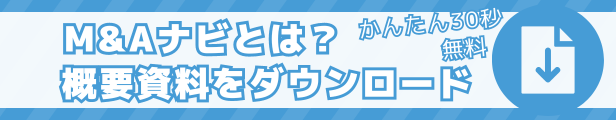





 メールで受けとる
メールで受けとる





