【2025年最新】ベンチャー企業のM&Aの市場動向!バイアウトの事例や3つのポイントを解説

ベンチャー企業のM&A市場は、グロース市場の上場基準の引き上げや100億宣言といった取り組みが影響し、件数増加や取引金額の高額化といった動きがあります。
また、2013年以降に急速に拡大したベンチャーキャピタルが、ファンド満期である10年を迎え始めていることから、Exitとしてスタートアップ企業のM&Aが増加している状況もあります。
日本におけるIPO(新規公開株式)の件数が微減となっており、今後も大幅な増加は見込めないためスタートアップの新しい出口戦略の一つとしてM&Aが活用されているという背景もありそうです。
そこでこの記事では、ベンチャー企業のM&Aに関する最新動向や価格相場、戦略のポイントを解説し、ベンチャーM&Aの成功の鍵を解き明かします。
この記事を読むことで、ベンチャー企業のM&Aに関して学ぶことができ、M&Aに対する不安や疑問点を解消できるでしょう。
記事だけでは解決できない不安や疑問は、経験豊富なアドバイザーがご相談を承っております。
まずは無料相談から!ぜひご連絡ください。
目次
ベンチャーのM&A市場の最新動向(2025)

近年、日本におけるスタートアップ企業のM&A件数は増加傾向にあります。
2023年にはスタートアップ企業によるM&Aが123件に達し、過去最高水準となりました。2024年もM&A件数はさらに伸び、2025年前半(1〜6月)には買収・子会社化が72件観測され、前年(2024年)の記録的水準に迫るペースで推移しています。
特に大企業による積極的な買収(いわゆる「攻めのM&A」)が広がっており、2025年上半期に日本企業が実施した国内外のM&A総額は約31兆円(前年同期比3.6倍)に上りました。
この背景には、新規株式公開(IPO)の停滞や東京証券取引所グロース市場の上場維持基準見直し(2030年より上場5年後に時価総額100億円以上へ厳格化)といった環境変化もあり、IPOに代わるEXIT手段としてM&Aを重視する動きが加速しています。
政策・制度がアップデート:スタートアップ育成計画と市場整備
政府もベンチャーM&Aの活性化に向けた制度整備を進めています。
岸田政権下で策定された「スタートアップ育成5か年計画」(2022〜2027年)では、スタートアップへの投資額10兆円、ユニコーン企業100社創出など大胆な目標が掲げられ、スタートアップのEXIT多様化が重要な柱と位置付けられました。
実際、日本のスタートアップのEXITは従来IPO偏重でしたが、政府は既存企業とのオープンイノベーション推進策としてM&A比率を高める方針を示し、税制優遇など環境整備を行っています。
特にオープンイノベーション促進税制の拡充は注目すべき制度変更です。従来はスタートアップへの新規出資が対象でしたが、2023年度税制改正で「M&A型」制度が創設され、スタートアップの発行済株式を50%以上取得する買収についても投資額の25%を課税所得から控除できるようになりました。この優遇措置により、大企業がスタートアップを買収するインセンティブが高まり、オープンイノベーション型のM&Aが一層促進されると期待されています。
また、未上場株式のセカンダリーマーケット整備も進展しています。2023年には改正金融商品取引法の施行や日本証券業協会の新規則制定により、証券会社が運営する私設取引システム(PTS)上で非上場株式の売買が可能となりました。この制度整備により、スタートアップの株式をベンチャーキャピタルや事業会社が上場前に売買しやすくなり、創業者や初期投資家にとってEXIT機会の多様化が図られています。
スタートアップ育成5か年計画でも「未上場株のセカンダリー市場整備」が掲げられており、今後は未上場株式の流動性向上によってM&Aを含む多様な出口戦略がさらに円滑化する見込みです。
ベンチャーM&Aのバリュエーション(企業価値評価)の考え方

スタートアップ企業の適正なバリュエーション(企業価値評価)は、M&A交渉の成否を左右する重要ポイントです。
通常の中堅・大企業のM&Aでは、EBITDA倍率や純資産など財務指標に基づく評価が多く用いられますが、スタートアップの場合は利益が出ていないケースや将来成長性が極めて高いケースが多いため、評価手法も一筋縄ではいきません。
スタートアップM&Aで用いられる評価手法
一般的には複数の手法を組み合わせて企業価値を算定します。
例えば、将来の事業計画に基づくDCF法や、同業他社のM&A実績から算出した売上高倍率・ユーザー数倍率等のマルチプルがよく用いられます。
スタートアップの場合、売上高やユーザーベースなど非財務的な要素や成長余地も重視され、定性的評価も加味して総合的に算定されます。
特に上場前の未成熟企業では会計上の数値だけで測れない価値が多分にあり、ケースバイケースで柔軟な評価が求められます。
評価額を巡るポイント
買い手である大企業にとっては、将来シナジーや技術の価値も考慮しつつも現実的な収益性やリスクを織り込んだ価格を提示することが重要です。
一方、売り手のスタートアップ側は、自社をIPOした場合の時価総額見込みなど高い期待値で評価しがちなため、IPO前提のバリュエーションとM&A前提のバリュエーションのギャップが交渉上の論点になります。
この乖離を埋めるために、たとえばアーンアウト条項を設定したり、一定期間後に再評価するオプションを付与したりといった工夫が行われる場合もあります。
また、スタートアップM&Aでは買収金額だけでなく株式交換比率やストックオプションの処理など検討事項も多岐にわたります。
未上場企業の評価額は客観的指標が少ないため、お互いの認識に差が出やすい点を踏まえ、独立第三者の評価を参考にしたり丁寧な説明によって合意形成を図ることが大切です。
適切なバリュエーション設定は、単に価格交渉だけでなく買収後の関係構築(売り手の納得感)にも影響するため、公平で納得性のある評価プロセスが成功の前提となります。
ベンチャーにおけるM&Aのメリット3選

ベンチャー企業のM&Aには多くのメリットがあると考えられています。
これらの利点は、企業が直面する困難や成長戦略を大きく左右し、企業の将来像を形成する重要な要素となります。
以下では、ベンチャー企業がM&Aを通じて享受できる主要なメリットを3つ紹介します。
経営戦略の多様化
ベンチャー企業はしばしば、市場の変動や成長段階に応じて柔軟な経営戦略が求められます。
M&Aは、これらの企業にとって、自社の資源を拡大し、新たな市場への進出や技術獲得のチャンスを提供します。
これにより、企業は長期的な成長戦略を多様化し、持続可能な成長への道を築くことができます。
シナジーと迅速な資金調達
ベンチャー企業にとってM&Aは、シナジー効果を生み出し、事業のスケールアップを可能にします。
買収により、製品開発、市場進出、運営の効率化など、さまざまな面で相乗効果を期待できます。
また、資金調達はベンチャー企業にとって永遠の課題ですが、M&Aを通じて必要な資金を迅速に調達し、成長機会をつかむことができます。
買い手売り手双方にメリットがあることが多い
M&Aは、買収する側とされる側の双方にメリットをもたらします。これも大きなメリットと言えるでしょう。
一般的に、買収されるベンチャー企業は、資金繰りの改善や経営リソースの強化といった即時の利益を享受できる一方、買収する側は、新しい市場へのアクセスや重要な技術の獲得、経営資源の最適化など、長期的なビジネス拡大に資するメリットを得られます。
ベンチャーにおけるM&Aのデメリット3選

ベンチャー企業にとってM&Aは多くの機会をもたらしますが、一方でデメリットも存在します。
ここでは、ベンチャー企業がM&Aを進める際に慎重に考慮すべき3つの主要なデメリットについて解説します。
組織文化の融合の困難
M&A後には、異なる企業文化を持つ組織が一つに統合されます。
ベンチャー企業特有の柔軟でイノベーションを重視する文化が、大企業の形式的で階層的な文化と衝突することがあります。
この文化の違いは、社内コミュニケーションの障害、チームワークの低下、最終的にはプロジェクトの遅延やパフォーマンスの低下を招く可能性があります。
経営陣と社員の不安
M&A後は経営陣や社員に多大な不安が生じることがあります。
特にベンチャー企業の場合、創業者やキーメンバーが経営方針に大きな影響を持つため、M&Aによる権力の再配置や将来性への不確かさは不安やモチベーションの低下を引き起こすことがあります。
これは、企業の戦略的な決定過程や日常の業務にも悪影響を及ぼす可能性があります。
イノベーションの減速
ベンチャー企業はしばしば、迅速な意思決定とイノベーションによって市場での競争優位を築きます。
しかし、M&A後には、新しい統合企業の規制やプロセスに適応する必要があり、これがイノベーションの速度を減速させることがあります。
特に大企業に吸収された場合、ベンチャー企業が持つ柔軟性と迅速性が損なわれることがあり、これが市場での優位性の低下につながる可能性があります。
ベンチャーのM&A成功への3つのポイント

ベンチャー企業のM&A成功は、単なる幸運ではなく、戦略的な計画と精緻な実行の結果です。
成長と発展の機会を最大限に活用するためには、市場の動向を正確に理解し、競争の激しい市場で独自の地位を築き、売却の最適なタイミングを見極めることが不可欠です。
以下では、ベンチャー企業がM&Aを成功に導くための3つの重要なポイントを詳しく解説します。
トレンドの捉え方
成功への第一歩は市場のトレンドを正確に捉えることから始まります。
ベンチャー企業は、新興技術や業界の変化を先読みし、これらのトレンドを自社の事業戦略に組み込む必要があります。
例えば、過去にはITバブルやモバイル革命がM&Aの風景を塗り替えました。
現在では、AI、ブロックチェーン、持続可能性に関するイノベーションなどが注目されています。
市場のトレンドを捉え、その波に乗ることで、ベンチャー企業は買収側企業からの価値ある注目を引くことができます。
市場の独占
市場における独自の地位を築くことは、M&A成功のための鍵です。
競合が少ないニッチ市場を見つけ出し、その市場で圧倒的な存在感を示すことが重要です。
これにより、ベンチャー企業は買収企業にとって魅力的な投資対象となります。
独占的な市場地位は、技術革新、顧客基盤の確立、あるいは特許や独自のビジネスモデルによって達成されることが多いです。
競合のいない市場での独占は、ベンチャー企業を独特で価値の高いM&Aの候補にします。
売却のタイミング
最後に、売却のタイミングはM&Aの成功において極めて重要です。
市場がピークに達したときや、企業の成長が加速している段階でM&Aを行うことで、最大限の価値を実現することができます。
逆に、市場が下降傾向にある時や、企業が財務的な困難に直面している時にM&Aを行うと、価値が低下する可能性があります。
売却のタイミングを見極めることで、ベンチャー企業は自社の真の価値を反映した条件でM&Aを成功に導くことができます。
これらのポイントは、ベンチャー企業がM&Aを通じて成功を収めるための重要な要素です。
市場のトレンドを的確に捉え、独自の市場地位を確立し、適切なタイミングでM&Aを実行することで、ベンチャー企業は次の成長段階へと進むことができます。
売却に必要な期間やM&Aを実施するタイミングに関しては、以下の記事をご確認ください。

【最短2カ月⁈】M&Aに必要な期間とは?はじめ...
M&Aが成約するにはどの程度の期間が必要なのでしょうか。 M&Aの際に用いる手法によって変わりますが、短くて半年間・長い場合は数年間ほどの期間を要することが一般的です。 必要な期間だけを聞くと、「なぜ…
ベンチャーのM&Aの成功事例3選

事例1. ブルックマンテクノロジによる凸版印刷への株式譲渡
ブルックマンテクノロジは、静岡大学の研究を起点に設立されたベンチャーで、主にCMOSイメージセンサの開発と設計に特化しています。
これらのセンサは、デジタルカメラやスマートフォンに必須で、光を電気信号に変換して画像を生成します。
凸版印刷は、印刷業界のリーダーであり、印刷技術を基盤に多岐にわたる事業を展開しています。
3Dイメージセンサ市場の成長に対応し、凸版印刷は2017年の提携を更に深め、ブルックマンテクノロジを子会社化しました。
2021年3月、凸版印刷はブルックマンテクノロジの発行済株式の大部分を取得し、共同で技術革新と市場拡大を進める体制を強化しました。
事例2.FacePeerによるマイナビへの株式譲渡
FacePeerは、幅広い場面で利用可能なビデオ通話プラットフォーム「FACEHUB」を中心に、業務効率化や働き方改革向けのITサービスを提供するベンチャーです。
マイナビは、人材紹介や情報提供サービスを提供する大手企業です。
2017年の提携後、両社はサービス連携を進めてきました。新型コロナウイルスの影響によりオンラインコミュニケーションの需要が拡大し、「FACEHUB」の普及を目指し、マイナビはFacePeerの株式を取得し、子会社化しました。
事例3. お金のデザインによるSMBC日興証券への会社分割
お金のデザインは、AI搭載ロボアドバイザー「THEO」を提供するFinTechベンチャーです。
このサービスは投資運用と証券取引を統合しています。
SMBC日興証券は、広範な証券サービスを提供する三井住友フィナンシャルグループの一員です。サービスの強化と安定化を目指し、お金のデザインは証券取引関連業務をSMBC日興証券に移譲しました。
このM&Aは、SMBC日興証券が進めるデジタルサービス強化戦略の一環です。
2021年1月、SMBC日興証券はお金のデザインから証券取引業務を継承し、同年8月に効力が発生しました。
参考:株式会社お金のデザインとの会社分割(吸収分割)契約締結に関するお知らせ
売却検討中の方の疑問をいますぐ解決!よくある質問と回答はこちら

M&Aでよくある質問〜売却検討中の方の不安・...
M&Aで会社や事業の売却を検討する中で、不安や疑問点は多くあるのではないでしょうか。 M&Aナビにおいても「いくらで売れるのか知りたい」「売却後の税金が不安」といったご質問をいただいております。 そこ…
ベンチャーM&Aにおける注意点・課題

最後に、ベンチャーM&A特有の注意すべき課題を整理します。
これらの点に予め留意し対策しておくことで、失敗リスクを低減できます。
Exit観点の違いによる価格の乖離
前述のように、スタートアップ側(特にVC出資企業)は将来の高成長を織り込んだ評価を志向しがちですが、買い手企業は現在の実績や会計上の整合性を重視するため、IPO前提とM&A前提で評価額にギャップが生じやすいです。
このズレを埋められず折り合えないと交渉決裂の恐れもあります。
お互いの前提条件を開示し、第三者評価も参考にしながら、現実的かつ将来に希望の持てる価格設定を探る努力が必要です。
株主・株式構造の複雑さ
スタートアップには優先株や種類株が発行されていたり、複数の投資契約上の権利条項が存在する場合があります。
これらをM&Aに伴いどのように処理・解消するかは専門的かつ繊細な交渉ポイントだといえるでしょう。
優先株の転換条件や清算条項の扱いなど、既存株主間の利害も絡むため、法務顧問を交えて慎重に対応する必要があります。
特に主要VCとは事前に意向をすり合わせ、彼らの期待IRRに配慮した提案を準備しておくことが望まれます。
カルチャーギャップへの対処
企業文化や意思決定スピードの違いはベンチャーM&A最大の難所です。
買収側の論理で押し通すとスタートアップの良さが失われ、人材流出や業績悪化に繋がりかねません。
スタートアップ・ベンチャー企業には、意思決定の早さや企業文化を魅力に感じることで入社する社員が多く在籍しています。
それらの企業文化がスタートアップ・ベンチャー企業としての対象企業の価値の本質となっている可能性があることを考慮しましょう。
双方が相手の文化を理解・尊重し、新しい共同体文化を作るくらいの姿勢が求められます。
統合後しばらくは対話を密にして現場の声を吸い上げ、小さな不満や摩擦も見逃さず解消していく丁寧さが重要です。
法規制や手続面のチェック
業種によっては独占禁止法上の企業結合審査や各種許認可の承継手続きなど、クリアすべき制度上のハードルもあります。
特に金融、医療、通信など規制産業のスタートアップを買収する場合、関係当局との調整や届出が必要となるケースがあります。
スケジュールに予備期間を持たせ、専門家の助言を仰ぎながらコンプライアンス面を確実にクリアすることも忘れてはなりません。
以上の点に注意しつつ準備を進めれば、ベンチャーM&Aのリスクを低減し成功確率を高めることができます。スタートアップ特有の不確実性やスピード感に振り回されず、冷静にリスクと向き合い計画的にプロセスを管理することが肝心です。

M&Aによる会社売却を従業員・社員に公表する...
M&Aによる会社売却を従業員や社員に公表することにより、信頼関係が崩れたり・不信感を持たれてしまうのでは? そんな不安を持たれている方も多いのではないでしょうか。 実際、公表するタイミングを少し間違えると、M&…
【ベンチャー M&A】まとめ

ベンチャー企業のM&A市場は、バイアウト件数の増加や取引金額の高額化といった特徴を通じて、その活発性を示しています。
この記事では、市場の活況、価格相場の動向、M&Aの利点とリスク、成功への要点、そして実際の成功事例を深掘りしました。
ベンチャー企業がM&Aを最大限に活用し、潜在的な課題を克服するための戦略的アプローチと、注意すべきポイントを明確にすることで、読者はこの複雑な市場の本質を理解し、有効な戦略を立てるための洞察を得ることができます。
M&Aナビは、買い手となりうる企業が数多く登録されており、成約までの期間が短いことが特徴です。ぜひご活用ください。

株式会社M&Aナビ 代表取締役社長。
大手ソフトウェアベンダー、M&Aナビの前身となるM&A仲介会社を経て2021年2月より現職。後継者不在による黒字廃業ゼロを目指し、全国の金融機関 を中心にM&A支援機関と提携しながら後継者不在問題の解決に取り組む。著書に『中小企業向け 会社を守る事業承継(アルク)』
関連記事

M&Aは個人でもできる?個人が中小企業をM&Aで買収する方法とは
個人M&Aが書籍やTVなどのメディアで大きく取り上げられ、「自分もできる!」「個人でM&Aして社長になりたい!」といった意欲のある方が増えて

M&Aはどこに相談するのが良い?相談先の選び方や、選ぶときの3つの注意点を徹底解説!
M&Aを検討しているが、どこに相談すればいいかわからない…。そんな悩みを抱えるは当然です。 家族や従業員に気軽に相談できる内容ではないですし、銀行や税

M&Aの売却価格はどう決まる?~相場・目安や売却価格の算出方法を解説~
M&A取引において、売却価格はどう決まるのでしょうか?また、売却価格に相場はあるのでしょうか。 いざM&Aで会社や事業を売却するとなれば、最

中小企業の事業承継におけるM&Aのメリットと高く売却できる条件とは?
本記事では、事業承継の手段としてM&Aを活用することのメリットや高く売却できる条件について解説します。 近年、親族や従業員への事業承継ではなく、第三者
新着買収案件の情報を受けとる
M&Aナビによる厳選された買収案件をいち早くお届けいたします。





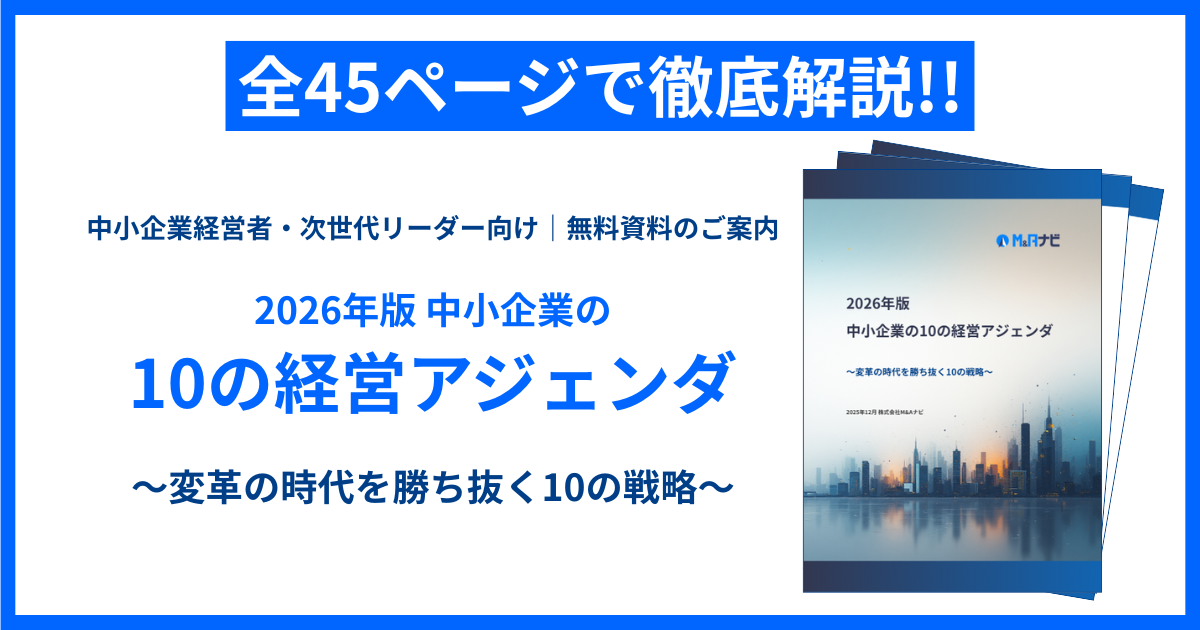
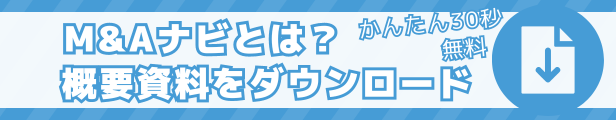



 メールで受けとる
メールで受けとる





