仲介って本当に必要⁉M&A支援会社がお伝えするM&Aアドバイザーの業務と支援の流れ
中小企業において、M&Aという戦略をとる企業が徐々に増えてきました。
元は後継者不在の中小企業のオーナー経営者の事業承継の選択肢の一つとして検討が広がったM&Aですが、最近では”成長戦略型M&A”という言葉が生まれ、よりすそ野が広がってきたように感じます。
弊社が運営するM&Aナビでは、個人事業主として運営してきた事業の売却の相談を受けることもあります。副業として運営する事業の売却やスモールビジネスの出口戦略としてもM&Aが選択される環境ができてきたといえるでしょう。
一方で、M&A仲介業界に関しては、一部報道にもあるように”吸血型M&A”に関与するような業者が出てきており、業界全体の動向が注目されているといえるでしょう。
そこで、今回はM&Aの支援者の仕事内容や必要性について解説し、皆様がM&Aで売却を検討する場合に必要な情報提供をいたします。
特に、いま話題になっているM&A仲介業に関して解説しますので、最後までお楽しみください。
目次
M&A仲介とプラットフォームの違いと、それぞれの役割
まず最初に、近年中小企業のM&Aを支援する方法として一般的な形だと考えられる、「仲介」と「プラットフォーム」の違いについて考えましょう。
仲介とマッチングサイトの本質的な違いとは?
M&Aを検討する際、支援方法として大きく分けて「仲介型」と「プラットフォーム型(マッチング型)」の2つがあります。
一見似ているように見えるこの2つの手法ですが、その本質には明確な違いがあります。
仲介型は、M&Aアドバイザーが売り手と買い手の間に立ち、条件交渉・資料整備・スケジュール管理・契約締結に至るまでを一貫してサポートします。
専門性が高く、複雑な利害調整が必要な中小企業のM&Aにおいては特に効果的なアプローチです。
一方、プラットフォーム型は、売り手と買い手が自身で情報を登録・閲覧し、直接やり取りする形式です。
コストを抑えやすくスピード感がある一方で、交渉・契約・リスク管理などは利用者自身の判断と責任に委ねられます。
どちらの方法が適しているかは、案件の性質や当事者のリテラシーに大きく左右されます。
株式会社M&Aナビでは、M&Aの仲介とM&Aプラットフォームの両方の形で支援をしています。
どちらが良い進め方かご不安があれば、お気軽にご相談ください。
M&Aナビが両方を手がける理由
M&A支援業界の多くのプレイヤーは、仲介かプラットフォームか、いずれかに特化する傾向があります。
しかし、私たちM&Aナビは、どちらか一方に絞るのではなく、両方のモデルを自社で運営しています。
これは、M&Aにおけるニーズや状況が多様化しており、それぞれの企業に合った最適な支援方法を提供するためです。
実際、初期段階では匿名で市場の反応を確かめたいというニーズからプラットフォームを利用し、途中から「やはりプロに任せたい」と仲介へ移行するケースは珍しくありません。
また、多くのM&A仲介会社は、”専門家ユーザー”としてM&Aプラットフォームに支援している案件を掲載し、買い手とのマッチングを促進している状況があります。
実際、弊社のM&Aプラットフォームにおいても”専門家ユーザー”が500ユーザーを超えていることから、プラットフォームの需要が高いとわかっていただけるかと思います。
M&Aナビはその両方をワンストップで対応できるます。
そのため、企業側の手間を最小限に抑えた柔軟な支援が可能になります。
また、両モデルを自社で運営するからこそ、成約に至った企業の特徴や、途中で失敗した理由など、成功と失敗の両方のデータを蓄積し、それを支援の現場にフィードバックできるという強みもあります。
状況に応じて使い分ける最適な選択肢とは?
どちらの支援スタイルが向いているかは、会社ごとの状況によって異なります。
たとえば、シンプルな事業譲渡や買い手からの明確な引き合いがある場合は、プラットフォームを活用して自主的に進める方法が有効です。
一方で、従業員の雇用継続や顧客・取引先への影響など、慎重な調整が求められる場合は、仲介型の支援が適しています。
経営者自身がM&Aの進め方に迷いがあるときこそ、支援会社の「使い分け提案力」が問われます。
M&Aナビでは、初期のご相談からその企業の置かれている状況やご希望を丁寧にヒアリングし、プラットフォーム・仲介いずれが最適かを中立的にご提案できる体制を整えています。
単に「サービスを提供する」のではなく、最適な選択肢を一緒に考えるパートナーとして、M&Aをより安全に、より納得感のある形で進めていただけるよう支援しています。
M&A支援で求められる「情報の非対称性」を埋める技術とは?
次に、M&A支援が必要な理由について見ていきます。
主に、売り手と買い手の「情報の非対称性」を埋め、適切な条件に落とし込む、という観点でM&A支援業者の重要性があるといえるでしょう。
買い手と売り手、それぞれの見えている世界は違う
M&A取引の現場では、買い手と売り手が同じ案件を見ていても、それぞれ異なる視点で捉えていることが非常に多くあります。
売り手側は長年にわたって築き上げてきた事業に対して強い思い入れがあり、社内文化や従業員の頑張りなど、定量化しにくい価値を重視します。
一方で、買い手は将来的な収益性や統合後のシナジー、リスクやコストといった、より冷静で客観的な観点から評価を行います。
このような認識のギャップが「情報の非対称性」と呼ばれ、交渉の停滞やミスマッチの原因になることも少なくありません。
売り手が「この会社は従業員が優秀です」と話しても、買い手は「それを証明する定量データがない」と判断してしまうケースが典型です。
こうしたズレを解消するには、感情や背景を整理し、ビジネスとしての魅力とリスクを明確に伝える技術が求められます。
誤解を防ぐ「第三者的視点」とは
ここで重要となるのが、M&Aアドバイザーによる「第三者的な視点」です。
M&Aナビでは、売却を検討する企業オーナーの想いや背景を丁寧にヒアリングした上で、買い手にとって理解しやすい言葉に翻訳・構造化し、提案資料として整備します。
たとえば、技術力や従業員の安定性をアピールしたい場合には、過去の受賞歴や離職率のデータ、資格保有者の数などを整理し、一目でわかるような図表付きの資料にまとめます。
また、売上の増減だけでなく、背後にある業界トレンドや顧客構成の変化なども補足情報として追記し、単なる数字以上の「物語」を伝える工夫をしています。これらの整理された情報は、売り手自身が直接語るよりも、第三者が中立的に示すことで、買い手の信頼を得やすくなります。
私たちM&Aナビのように、マッチング型プラットフォームと仲介型支援の両方を手がけているからこそ、情報の構造化と可視化におけるノウハウを豊富に持っているのです。
PDFによる見やすい案件概要・比較資料の価値
このように整理された情報を届ける手段として、私たちはAdobeAcrobatProを日常的に活用しています。
特に、複数の情報ソースから得たデータを一つの提案資料に統合する作業において、PDFファイルの結合やページ順の調整、注釈の挿入機能により効率的に作業しています。
例えば、企業概要、財務資料、組織図、設備一覧といった異なるファイルを一つのPDFに統合し、AdobeAcrobatPro上でページごとの注釈を加えながら、読み手がどの順番で読むべきか、どの項目が特に重要かを明示します。
さらに、交渉が進みデューデリジェンスが始まると、買い手企業は、細かい契約書を含めて膨大な資料に対する調査を開始します。
M&Aアドバイザーは、「デューデリジェンス以降のフェーズにおいてM&Aの成立が困難になるような情報が見つかること」は避けなければなりません。
なぜなら売り手・買い手の両者がこれまで検討してきた時間が無駄になるからです。
そこで私たちは、AdobeAcrobatProのAI要約機能を活用しています。
商流に関する取引契約や労務関係の書類まで、売り手企業から収集した資料から「M&Aの成立を阻害するような契約内容は無いか」を効率的に調べることができます。
私たちは、単に「情報を届ける」だけでなく、「伝わるかたちで整える」「膨大な内容から重要なことを漏らさずに伝える」ことにこだわっています。
自力では難しい?アドバイザーが必要とされる理由
M&A特有の専門知識・法律・税務への対応力
M&Aは、単なる売買ではなく、法律・税務・会計・労務など、多分野の専門知識が複雑に絡み合う高度な取引です。
たとえば、譲渡対価の受け取り方法一つとっても、現金か株式か、前払金とアーンアウト(成果報酬)のバランス、株式譲渡と事業譲渡の違いによる税務影響など、判断ミスが後々大きな損失につながる可能性があります。
また、デューデリジェンス(DD)や基本合意書(LOI)、最終契約書(SPA)の作成・調整には、高度な契約スキームやリスクヘッジの知見が求められます。
弁護士や税理士と連携しつつ、現場の意思決定をサポートするのがアドバイザーの役割です。
自力で進めた場合、重要な論点が抜け落ちている契約になってしまうリスクは否めません。
相手先の選定・打診の網羅性とスピード
適切な買い手や売り手を見つけることは、M&Aの成否を分ける最初のハードルです。
しかし、経営者自身が手探りで相手を探そうとすると、情報不足や時間的制約により、本来出会えたはずの最適な相手にたどり着けないことも少なくありません。
アドバイザーは、独自のネットワークとデータベースを活用し、企業の業種・規模・地域性・意向などに合致した候補を短期間でリストアップすることが可能です。
また、打診のタイミングや手法にもノウハウがあり、事業の特性を踏まえて「売り込みすぎず、興味を惹く」絶妙な提案を行います。
仮に断られたとしても、その理由をフィードバックとして活かし、条件の見直しやターゲット変更をすばやく行える点も、アドバイザーならではの強みです。
M&Aはスピードも大切。
動き出しが遅れれば、良い買い手・売り手を逃してしまう可能性があります。
第三者が入ることで成立しやすくなる交渉
M&A交渉は、数字や条件だけでなく、感情や人間関係も絡むデリケートなやりとりです。
売り手から直接条件を提示された買い手が「強気すぎる」と感じたり、逆に売り手が「上から目線だ」と受け取ってしまったりすることは珍しくありません。
こうした場面で効果を発揮するのが、アドバイザーという“緩衝材”の存在です。
第三者としての中立的な立場で双方の意見を受け止め、必要に応じて条件の背景を翻訳し、相手に伝える。
一度こじれかけた交渉を建設的な方向に戻す「調整役」として機能します。
また、買い手・売り手の間に感情的なすれ違いがあったとしても、アドバイザーが冷静に整理しながら進行することで、両者にとって納得感のある合意形成が可能になります。
こうした交渉技術は、一朝一夕で身につくものではなく、多くの実務経験を経て培われるものです。
M&Aは単なる取引ではなく、企業の未来に関わる重要な意思決定です。
だからこそ、自力で進めるのではなく、信頼できる専門家の伴走を得ることで、後悔のない着地を実現できる確率は格段に高まります。
信頼できるアドバイザーを選ぶためのチェックポイント
過去の成約実績と得意な業界・規模の確認
M&Aアドバイザーを選ぶ際に、まず確認すべきは「これまでにどのような実績があるのか」という点です。
M&Aは業界ごとに商習慣や収益モデルが大きく異なるため、単に「成約件数が多い」だけでは不十分です。
自社と同業種・同規模の企業に対して、どれだけの理解と支援経験があるかを確認する必要があります。
また、実績と合わせて注目したいのが、交渉・書類作成・金融機関との連携など、表に出ない部分も含めて、どこまで深く関与しているかを確認することです。
単なる「マッチング」ではなく「解決支援」としてのM&A支援力が見えてきます。
アドバイザーの公式サイトに掲載されている成約事例や、お客様の声なども参考になりますが、実際の打ち合わせの中で「自社と似たような案件でどのような提案・支援をしたか」を具体的に聞くのが最も有効です。
担当者の人柄・姿勢・対応スピード
M&Aは、一度契約したら終わりではなく、数ヶ月〜1年にわたる長期のプロジェクトになります。
だからこそ、担当者との相性は非常に重要です。
「話が伝わりやすいか」「スケジュール感が合うか」「こちらの希望に誠実に向き合ってくれるか」など、一緒に走っていけるパートナーであるかを見極めましょう。
特に重要なのは、初回面談や資料のやり取りなど、ちょっとしたやりとりのスピード感です。
返信が遅かったり、質問への答えが曖昧だったりするような場合は、後々の対応にも不安が残ることになります。
最初の印象こそが、継続的な信頼関係を築けるかどうかのヒントになるのです。
また、業者によっては担当者が途中で変わったり、実務を外部に任せるケースもあるため、「自分の窓口になる人が誰で、どこまで関与してくれるのか」についても確認しておくことをおすすめします。
報酬体系の透明性とリスクの少なさ
M&A支援を受ける上で、費用に関する不安は誰もが抱えるポイントです。
仲介手数料は数千万円に及ぶこともあり、「こんなにかかると思わなかった」と後悔するケースも少なくありません。
そのため、報酬体系が明確であるかどうかは、アドバイザー選定における重要な基準となります。
一般的には、着手金・中間金・成功報酬の3段階で構成されますが、その内訳や計算方法(レーマン方式など)が複雑なこともあります。
契約前に「いつ・何に対して・いくらかかるのか」を納得いくまで説明してもらいましょう。
また、万一M&Aが成立しなかった場合に、どれだけの費用が発生するのかも事前に確認すべき点です。
成功報酬型(完全成果報酬)のアドバイザーであれば、リスクを抑えつつ、安心して依頼しやすくなります。
最終的には、「価格に見合うだけの支援価値があるか」を見極めることが大切です。
関連記事
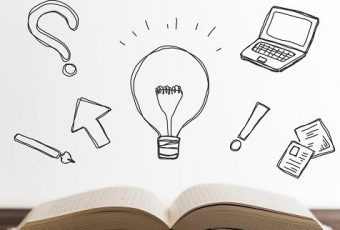
M&Aにおける仲介とFAの違いとは?立場・役割や選び方、手数料について
M&Aの支援機関には、M&A仲介とFA(フィナンシャルアドバイザー)という2つの形態があります。 そこで本記事では、M&A仲介とF

M&A仲介とは?FAとの違い・業務範囲・メリット・費用・注意点を解説
本記事では、M&A仲介とは何かを基礎から解説します。 FAとの違い、業務範囲、メリット、費用、注意点(選び方のポイント)、課題やプラットフォームとの違
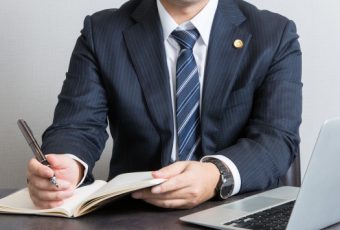
M&A仲介会社の選び方や費用について解説!2つのポイントと3つの注意点が丸わかり
以前よりもM&Aが経営戦略の一つとして一般的になるにつれて、M&A仲介会社の選び方がポイントとなっています。 経済産業省も「中小M&A推進計

M&Aのデューデリジェンス(DD)とは?目的や期間・注意点を解説!
M&Aにおいてデューデリジェンス(DD)がどのような役割を果たすかを理解しないまま戦略を練っている方は多いのではないでしょうか。 M&Aを実
新着買収案件の情報を受けとる
M&Aナビによる厳選された買収案件をいち早くお届けいたします。










 メールで受けとる
メールで受けとる





