M&Aで会社売却する場合の経営者保証の取扱いは?注意点も解説!
中小企業のM&Aを検討する経営者にとって、「譲渡後の経営者保証の解除」は大きな不安の種です。
会社を譲渡して経営から退いたにもかかわらず、会社の借入に自分個人の保証が付いていると、買い手の対応次第では自宅や個人資産で借金を返済し続けなければならないリスクが残ります。
実際、M&A後に買い手が経営者保証の解除を怠り、売却後の元オーナーが会社債務の返済に苦しむというトラブルが問題になっています。
こうした不安から「会社を譲りたいが借金の個人保証がネックだ…」と事業承継を躊躇している方も多いでしょう。
幸い、中小企業庁のガイドライン改訂や業界団体の自主ルールにより、買い手企業に対して売り手オーナーの保証解除を確実に履行させる仕組みも整いつつあります。
本記事では、M&Aや親族内承継の際に経営者保証を外すための最新ポイントを解説します。経営者保証がM&Aの障害とならないよう、契約条項の工夫や公的支援制度の活用など押さえておくべき対策を確認しましょう。
目次
経営者保証とは
まずは経営者保証について理解を深めましょう。
経営者保証の概要
経営者保証とは、中小企業の経営者が会社が借り入れた資金に対して個人的に保証を行う制度です。
主に金融機関からの融資を受ける際に必要となり、経営者自身が会社の借入金返済の責任を負うことを意味します。
会社が倒産した場合、経営者個人が自宅や預金など私財を投げ打ってでも借金を返済しなければならず、下手をすれば個人破産に追い込まれかねません。
経営に失敗すれば個人の生活再建も困難となるため、経営判断が萎縮し「思い切った事業展開ができない」原因にもなります。
特に中小企業では、会社単体での信用力が足りないことが多いため、経営者が個人的に保証を提供することが一般的です。
中小企業では長年一般的な慣行であり、経営者保証のおかげで資金調達が円滑になるメリットもあります。
つまり、銀行や金融機関は、経営者保証を求めることで企業の借入金に対するリスクを軽減することができ、融資の確実性を高められます。
日本においては、多くの中小企業がこの仕組みを利用して資金を調達しており、経営者にとっては欠かせない制度となっています。
経営者保証の課題
経営者保証には、経営者にとって非常に大きなリスクが伴うことが課題とされています。
企業の経営状況が悪化して倒産に至った場合は、経営者は個人の資産を差し出してでも借入金を返済しなければならず、経営者自身の生活や財産にも大きな影響を与えます。
このため、経営者保証は事業失敗のリスクを個人に集中させる結果となります。
特に、事業承継時の大きな障壁になる点が近年特に問題視されています。
実際、中小企業基盤整備機構の調査によれば、後継者候補がいるにもかかわらず事業承継を拒む理由のトップが「経営者保証の負担」だったとの報告もあります。
このように経営者保証は中小企業経営者に重くのしかかるリスクであり、その在り方を見直す動きが進んでいます。
見直しの取り組み
近年、経営者保証に対する見直しの取り組みが進んでいます。
特に、日本政府や金融機関は、中小企業の成長や事業承継を促進するため、経営者保証の負担を軽減する方策を導入しています。
「経営者保証に関するガイドライン」が制定され、企業の財務状況や経営者の経営責任が明確に分離されている場合には経営者保証を不要とする方向で金融機関が対応することが推奨されています。
このガイドラインに基づき、一定の条件のもとで経営者保証を外すことが可能となります。
経営者保証の見直しは、経営者にとって大きな負担軽減にとどまらず、事業承継やM&Aを円滑に進めるための重要な要素となっています。
経営者保証は中小企業にとって重要な制度でありながら、課題を抱えている状況だとえいます。
中小企業庁が見直しの取り組みを進めており、今後は経営者の負担を軽減し事業の持続的な成長をサポートする制度へと進化していくことが期待されています。
経営者保証が必要とされる理由
経営者保証は、中小企業が資金調達を行う際に一般的に求められるものです。
特に、金融機関は企業単体の信用力だけでは十分な融資を行うことができないと判断した場合、経営者の個人的な保証を要求することが多くあります。
ここでは、経営者保証がなぜ必要とされるのか、その理由を3つの観点から解説します。
信用力の補完
中小企業は大企業に比べて、財務基盤や信用力が弱いことが一般的です。
設立間もない企業や成長過程にある企業では、財務状況が安定しておらず企業単体での融資申請が難しい場合があります。
このような場合、金融機関は経営者個人の信用力を補完的に利用することで、融資を実行するケースが多く見られます。
経営者保証は、企業の債務に対して経営者が個人的に責任を負う形となるため、金融機関にとってはリスクヘッジの一環として機能します。
万が一、企業が倒産した場合でも、経営者が個人資産をもって返済に充てることができるため、金融機関は融資のリスクを軽減できるのです。
特に中小企業にとっては、経営者保証を提供することで金融機関からの信用を獲得しやすくなるというメリットがあります。
債権者のリスク軽減
金融機関や債権者にとって、貸付金が回収できないリスクは常に存在します。
企業が万が一経営に行き詰まり、債務不履行に陥ると、金融機関は大きな損失を被る可能性があります。
このリスクを軽減するために、経営者保証が求められることが多くあります。
経営者が個人的に保証を提供することで、債権者は二重の保証を得ることができるため、貸し倒れのリスクを大幅に減少させることができます。
特に、中小企業のように経営が不安定な場合、金融機関は経営者保証を必須とすることが多く、これにより貸し付けに伴うリスクを管理します。
また、経営者が保証を提供することで、金融機関は安心して資金提供を行うことができるため、企業にとっては資金調達がしやすくなるという側面もあります。
経営への規律付け
経営者保証は、企業の経営者に対して強い責任感を持たせるための規律付けの手段としても機能します。
経営者が個人的に保証を行うことで、自らの資産が企業の経営結果に直結するため、経営者はより慎重かつ責任を持って経営判断を行うようになります。
これにより、企業の健全な経営が促進されると考えられています。
金融機関も、経営者保証を通じて、経営者に対して一定のプレッシャーをかけることができます。
経営者が個人的なリスクを背負うことで、事業運営における慎重な意思決定が促され、企業全体の経営が規律あるものとなることが期待されます。
特に、資金繰りや経営の透明性が求められる中小企業においては、経営者保証が一種の「安全装置」として機能することが多いです。
このように、経営者保証は企業の信用力を補完し、金融機関や債権者に対してリスクを軽減する手段として必要とされています。
同時に、経営者に対して規律を与える役割も果たしており、特に中小企業においては、経営者保証が資金調達を円滑に進めるための重要な要素となっています。
M&Aで会社を売却すると経営者保証はどうなるのか
M&Aを通じて会社を売却する際、経営者保証がどのように扱われるかは非常に重要な問題です。
多くの経営者にとって、事業売却によって自らの個人資産へのリスクを減らしたいという願いが強く、経営者保証を外す方向で交渉を進めることが一般的です。
しかし、M&Aの手法や取引条件によっては、経営者保証が残ってしまう場合や、交渉が難航することもあります。
ここでは、M&Aにおける経営者保証の取扱いについて解説します。
基本的に外す方向で進めるのが一般的
会社を売却する際、多くのケースで経営者保証は解除されるか、交渉により外す方向で進められるのが一般的です。
M&Aによって経営者が会社を手放す場合、その企業に対する経営責任も放棄することになるため、買い手としても経営者に保証を求め続ける理由がなくなります。
これにより、経営者保証を外すための交渉が通常行われます。
特に、買い手が財務基盤の強い企業やファンドである場合、経営者保証の解除に対する抵抗は少なく、スムーズに進むことが多いです。
しかし、買い手側の信用力が十分でない場合や、取引条件に不確定要素が多い場合には、経営者保証を完全に外すことが難しいケースもあります。
そのため、売り手と買い手の間で事前にしっかりと交渉を行い、保証の扱いについて合意を得ることが重要です。
手法によって考え方が変わる
経営者保証の解除がスムーズに進むかどうかは、M&Aの手法によっても異なります。
株式譲渡や事業譲渡といった異なるM&Aの形態に応じて、経営者保証の扱いも変わるため、取引の手法を慎重に選ぶ必要があります。
以下では、代表的な手法である株式譲渡と事業譲渡における経営者保証の扱いについて詳しく解説します。
株式譲渡
株式譲渡は、企業の株主が所有する株式を売却することで、経営権が移転するM&Aの手法です。
この場合、会社の法人格や資産・負債はそのまま維持されるため、原則として経営者保証もそのまま残ることが多いです。
したがって、経営者保証を解除するには、債権者(主に金融機関)と交渉し、保証の取り扱いについて事前に合意を得る必要があります。
株式譲渡における経営者保証の解除は、買い手が新たな保証を提供できるか、または企業の財務状況が改善されているかどうかに依存します。
買い手が十分な信用力を持っている場合や、買収後に企業の財務基盤が強化されると見込まれる場合には、金融機関も保証解除に前向きになることが多いです。
しかし、場合によっては部分的に保証を残す形での譲渡が行われることもあります。
事業譲渡
事業譲渡は、会社の事業や資産を選択的に売却する手法です。
この場合、売却対象となるのは企業の一部事業や特定の資産であり、会社全体が売却されるわけではありません。
事業譲渡では、株式の移転は行われないため会社の借入金や経営者保証に関しては、基本的にはそのまま売り手側に残ります。
一方で、事業譲渡ではその対価を買い手から受け取ることができるため、借入金の返済に充てることができます。
このように、M&Aにおける経営者保証の取扱いは、取引の手法や条件によって異なります。
経営者保証を解除するかどうかについては、買い手と売り手、そして金融機関との緊密な交渉が不可欠であり、事前にしっかりと合意を形成することが成功の鍵です。
経営者保証がM&Aで問題になる理由
近年では、会社売却時に経営者保証が厄介な問題となるケースが増えています。
一部のM&Aでは経営者保証の解除が不十分なままクロージングしてしまい、後から売り手にトラブルが生じる例が問題視されます。
具体的には、契約上ちゃんと保証解除の取り決めをしていなかったり、「解除に努める」といった努力義務止まりで買い手の法的責任が弱かったり、義務は定めても履行を担保する策が無かったりする場合です。
その結果、買い手が金融機関に働きかけず旧オーナーの保証が放置され、後になって売り手(旧社長)が個人資産で会社債務を支払わされる羽目に陥ります。これは売り手にとって悪夢のような状況です。
実際、一部では悪質な買い手が問題視されています。2021年前後から短期間に中小企業を約30社買収し、その後倒産させたり資産を持ち出したりした買い手のケースでは、旧オーナーが保証債務の返済に苦しみ訴訟になる事態も報じられています。
このように買い手による経営者保証未解除トラブルは、中小M&A市場における大きな課題となりました。
経営者保証トラブルを防ぐためのポイント
経営者保証の解除トラブルを避けるには、M&A契約の段階で万全の対策を講じておくことが不可欠です。
以下、契約上の重要ポイントを整理します。
経営者保証解除義務を明確に定める
まず、譲渡契約書に「買い手は取引実行日後速やかに経営者保証を解除すること」を明記しましょう。
保証解除について一切触れていない契約書は論外ですが、「できる限り努める」といった努力義務では不十分だといえるでしょう。
買い手の「義務」として保証解除を定めることで、契約違反による責任追及が可能な状態にしておきます。
履行を担保する仕組み(売却代金の一部留保等)
義務を定めても、それを確実に履行させる担保策がなければ意味がありません。
たとえば解除完了まで旧オーナーに連帯保証人としての求償権(買い手に肩代わり請求できる権利)を留保させるなど、買い手の不履行にペナルティが及ぶ条項を検討しても良いでしょう。
いずれにせよ、「解除義務+担保策」のセットで定めておくことで、契約上できる限り売り手を守ることが重要です。
金融機関と事前調整を行う
契約だけでなく、金融機関との事前交渉・調整も欠かせません。
中小企業のM&A実務では、売り手・買い手・金融機関の三者で保証解除の段取りを事前に協議しておくことが理想です。
多くのトラブルの背景には「銀行への根回し不足」があると指摘されています。
例えば、買い手が引き続き会社の借入を継続利用する場合は、銀行にとって債務者の代表者が交代することになります。
金融機関としては新経営者に改めて保証を求めるか、あるいは融資条件を見直す必要があります。
ゆえに、M&A契約前に銀行と「旧経営者の保証解除」と「今後の融資条件」について交渉・合意しておくことが、安全な事業承継の鍵となります。
銀行側もガイドラインにより「事業承継時には原則、前経営者と後継者の二重で保証を取らない」方針が示されていますので、誠実な買い手であれば協力して解除に動くのが通常です。
実務では、M&Aの最終契約締結と同時に銀行との間で旧保証人の解除契約を結ぶことも増えてきており、仲介者やFAが調整をサポートします。売り手オーナーは、自身の顧問弁護士や仲介会社に働きかけ、金融機関との三者間協議を確実にセットしてもらいましょう。
一定期間保証を残すケースへの対応
近年、一部では「クロージング後○ヶ月間だけ旧オーナーの保証を残す」という条件付きの契約も見られます。
例えば「売り手社長はM&A後6ヶ月間、従前と同様に会社業務に従事すること。その期間経過後に保証解除する」といった条項です。
これはPMI(買収後の経営統合)を円滑にするため買い手が求めるケースですが、保証が一時的にせよ残る以上、慎重な対応が必要です。
万一この間に買い手の対応が滞れば、売り手は引き続き連帯保証人としてリスクを負う可能性があります。売り手側の弁護士としては、場合によってはディールを中止する覚悟でも買い手や仲介業者と交渉すべきとの意見もあります。
要は、「○ヶ月後解除」の契約を結ぶなら、確実にその期限で解除される仕組みを組み込むべきです。安易に先延ばしを認めず、リスクは極力見える化・限定化しておくことが求められます。
経営者保証を解除する方法
経営者保証は、企業が融資を受ける際に経営者個人が会社の債務を保証する制度ですが、経営者にとっては大きなリスクとなります。
そのため、経営者保証を解除することは、経営者の負担を軽減し、企業の健全な成長を支えるために重要です。
ここでは、経営者保証を解除するための主な方法を3つ紹介します。
これらの方法を実践することで、経営者保証を外しやすい状況を整えることが可能になります。
法人と経営者との関係の明確な区分・分離
経営者保証を解除するための最も重要なステップの一つは、法人と経営者個人の関係を明確に区分・分離することです。
多くの中小企業では、経営者個人と企業の財務が密接に絡み合っているため、金融機関は経営者に保証を求めがちです。
経営者個人の資産と法人の資産が曖昧である場合、金融機関はリスク管理の観点から、経営者保証の解除を拒む可能性が高くなります。
法人と経営者個人の財務関係を分離するには、まず経営者が企業の資金と個人の資金を明確に区別することが必要です。
具体的には、法人の経費と個人の支出を混同しないことや、法人の資産・負債と個人の資産・負債を明確に区分することが求められます。
このように、法人と個人の経営責任を分けることが、経営者保証の解除に向けた第一歩となります。
財務基盤の強化
経営者保証を解除するもう一つの方法は、企業の財務基盤を強化することです。
企業の財務状況が健全であり、自己資本比率が高い場合、金融機関は経営者保証に頼らずに融資を実行する可能性が高まります。
特に、キャッシュフローが安定しており、負債の返済能力が十分にある企業であれば、経営者保証の必要性は大きく低減します。
財務基盤の強化には、まず企業の収益性を向上させ、安定したキャッシュフローを確保することが重要です。
また、資産を効率的に運用し、不要な負債を減らすことで、企業の財務状態を健全化することができます。
さらに、企業の成長戦略を明確にし、収益見込みをしっかりと金融機関に説明することで、経営者保証を外すための交渉を有利に進めることが可能となります。
財務状況の正確な把握・経営の透明性の担保
経営者保証を解除するためには、企業の財務状況を正確に把握し、経営の透明性を確保することも重要です。
金融機関が企業の経営状況や財務情報を正確に理解できない場合、経営者保証を外すことに対して慎重な態度を取ることがあります。
これを避けるためには、定期的な財務報告や監査を行い、経営の透明性を高めることが必要です。
具体的には、正確な会計処理を行い、外部監査を定期的に受けることが有効です。
また、企業の事業計画や成長見込みを金融機関に対して十分に説明することで、経営の信頼性を高め、経営者保証の解除に向けた交渉を円滑に進めることが可能となります。
透明な財務報告は、金融機関がリスクを正確に評価するための重要な要素であり、これを確保することで経営者保証の解除が現実的なものとなります。
このように、経営者保証を解除するためには、法人と経営者の財務関係を明確に分離し、企業の財務基盤を強化し、経営の透明性を担保することが求められます。
これらの取り組みを通じて、経営者保証を外し、企業のリスクを軽減することが可能となります。
M&Aにおける経営者保証に関する注意点
M&Aを行う際、経営者保証に関してはさまざまな注意点があります。
特に、売り手の経営者にとって、会社売却後も経営者保証が残るケースがあり、これを回避するための事前の準備が重要です。
ここでは、M&Aにおける経営者保証に関する主な注意点を3つ取り上げ、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
手法による違いがあること
M&Aにおいて経営者保証の取扱いは、取引の手法によって異なります。特に、株式譲渡や事業譲渡など、異なるM&Aの形態によって、経営者保証が外れるかどうかが左右されます。
株式譲渡では、企業の法人格がそのまま引き継がれるため、経営者保証が継続される可能性があります。
対して、事業譲渡では、企業の特定事業のみが譲渡されるため、経営者保証が外れるケースが多いです。
そのため、M&Aを計画する際には、取引の手法を慎重に選ぶことが重要です。
売り手側が経営者保証を外したい場合は、事業譲渡などの方法を検討することが有効です。
しかし、買い手の意向や取引の条件次第では、株式譲渡が適している場合もあるため、M&Aの手法を選定する際には専門家の助言を得ながら進めることが重要です。
譲渡時に勝手に外れるわけではないこと
M&Aを行えば、経営者保証が自動的に解除されると考える方もいますが、実際にはそうではありません。
売り手の経営者が会社を手放しても、保証契約が明示的に解除されない限り、経営者保証は残ります。
つまり、売却後も経営者が個人の資産で債務を保証し続けるリスクが存在するのです。
経営者保証を解除するためには、金融機関やその他の債権者との間で正式な手続きを踏む必要があります。
通常、売り手と買い手が締結する譲渡契約書において、経営者保証の解除の手続きを行うよう買い手に責任を付与することが一般的です。
これは、売却契約を締結する前に必ず確認しておくべき重要なポイントです。
特に、金融機関との交渉を円滑に進めるためには、財務状況の改善や新たな買い手の信用力など、保証を外すための合理的な理由を示すことが重要です。
債権者の承諾を得ること
経営者保証を外すためには、債権者の承諾を得ることが不可欠です。
特に、金融機関や主要な取引先が債権者である場合、経営者保証を解除するためには、これらの債権者が納得する条件を提示する必要があります。
売り手としては、企業の財務状況を整備し、信用力を高めることで、金融機関に対して保証の解除を求める交渉を進めることが可能です。
また、買い手が新たに保証を提供できる場合や、買収後に企業の財務基盤が強化される見込みがある場合には、金融機関も前向きに保証解除に応じることが多くなります。
そのため、事前に売り手と買い手、金融機関の三者でしっかりと交渉し、合意を得ておくことがM&Aを円滑に進めるための重要なステップとなります。
M&Aにおいて経営者保証は非常に重要な要素であり、その解除には手法や契約条件に応じた慎重な対応が必要です。
保証の解除が自動的に行われるわけではないため、事前に債権者との交渉や専門家の助言を受けることで、リスクを最小限に抑えた形でM&Aを進めることが可能となります。
M&Aで経営者保証を解除するには、手法や契約に注意が必要です。
法人と個人の区分や財務基盤の強化が重要で、債権者の承諾も欠かせません。
M&Aにおける経営者保証に関するまとめ
M&Aにおける売り手側のオーナーの関心ごとの中に経営者保証があります。
手法にもよりますが、適切な手続きを取ることができれば、ほとんどの場合、経営者保証の解除ができます。
M&Aにおける保証の手続きに関しては、M&A仲介会社やM&Aの専門家を活用するのが良いでしょう。

株式会社M&Aナビ 代表取締役社長。
大手ソフトウェアベンダー、M&Aナビの前身となるM&A仲介会社を経て2021年2月より現職。後継者不在による黒字廃業ゼロを目指し、全国の金融機関 を中心にM&A支援機関と提携しながら後継者不在問題の解決に取り組む。著書に『中小企業向け 会社を守る事業承継(アルク)』
関連記事
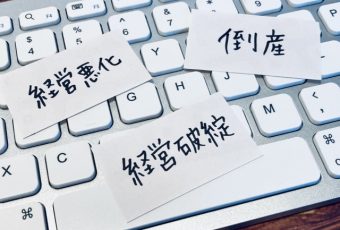
債務超過であっても会社売却はできる?成功のポイントや進め方について解説!
債務超過に陥った企業でも、適切なアプローチを取れば売却は十分に可能です。 本記事では、債務超過の会社が売却できる理由や、そのメリット・デメリット、売却を成功させ

会社を廃業すると借金はどうなる!?パターン別の対応方法を徹底解説!
会社の廃業を検討し始めたときに、「会社で借りている借金はどうなるのか?」と心配になるでしょう。 日本の中小企業のうち、どれくらいの企業が融資を受けているかご存知

赤字であっても会社売却はできる?成功のポイントや進め方について解説!
赤字企業であっても、適切な戦略と準備があれば売却は可能です。 本記事では、赤字企業を売却する際のメリットやデメリット、企業価値の評価方法、売却を成功させるための

M&A(エムアンドエー)とは?意味や目的、仕組みや手法などM&Aの基本を簡単に解説!!
M&A(エムアンドエー)とは、”Mergers and Acquisitions”の頭文字を取った略語であり日本語に直すと合併と買収です。 本記事では
新着買収案件の情報を受けとる
M&Aナビによる厳選された買収案件をいち早くお届けいたします。





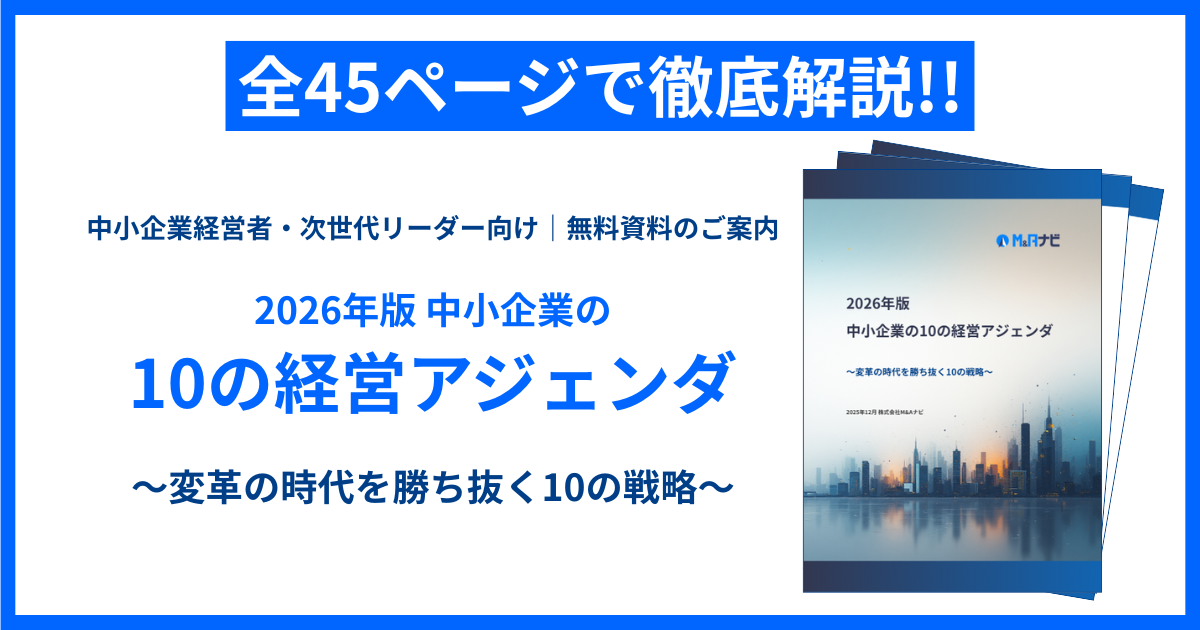
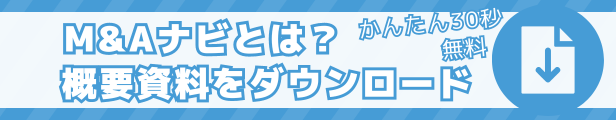




 メールで受けとる
メールで受けとる





