事業承継の失敗に学ぶ!よくある原因と対策、成功に導くポイントとは?
中小企業経営者の高齢化が進む中、「事業承継」は多くの企業にとって喫緊の課題です。
しかし、実際には承継後に業績が悪化したり、後継者がすぐに辞任してしまうといった「事業承継の失敗」が少なくありません。
なぜ失敗してしまうのでしょうか?本記事では、失敗事例とその原因、そして成功のためのポイントを解説します。
目次
なぜ事業承継は失敗するのか?
そもそも「事業承継の失敗」とはどういうことか?
事業承継の「失敗」とは、単に承継が実行されなかった場合だけを意味するわけではありません。形式的には承継が完了していたとしても、以下のような事態が起きれば、それは「失敗」と判断されるケースが多いです。
・後継者が就任後すぐに辞任してしまった
・社員や幹部との信頼関係が築けず、組織が混乱
・売上や利益が急落し、経営が不安定に
¥相続税や資産の分配トラブルで家族間の争いが発生
つまり、承継の「実施」そのものよりも、「承継後に企業が安定し、成長できているか」が問われるのです。
表面的な手続きが完了していても、持続可能な体制が築けていなければ、それは真の意味での成功とは言えません。
失敗に至る主な原因とは?
事業承継がうまくいかない背景には、いくつかの共通した原因があります。
1. 後継者育成の不足
経営者として必要な視点、判断力、人間関係の築き方は、短期間では身につきません。
現経営者が後継者に十分な経験の機会を与えないまま、形式的にバトンを渡してしまうと、承継後にさまざまな不安定要素が噴き出します。
2. 経営者と後継者の価値観の違い
創業者は「伝統」や「安定」を重視しがちなのに対し、後継者は時代に即した「変革」や「効率化」を志向する傾向があります。
方向性の違いが埋められないまま承継を進めると、組織内部に摩擦や分断が生まれ、従業員の不安や混乱を招くことになります。
3. 社員や取引先の反発
新体制に馴染めない社員が離職したり、取引先が「この先、大丈夫か?」と不安を感じて契約を見直すなど、信頼関係が揺らぐリスクがあります。
とくに、社内のキーパーソンが抜けると、業務や士気に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
4. 財務・税務の準備不足
相続税や贈与税の負担を見誤ると、事業資金が逼迫し、継続経営が難しくなるケースも少なくありません。
また、株式の分散によって経営権が不安定になると、意思決定のスピードが落ち、経営そのものが停滞してしまうこともあります。
5. 承継への心理的な準備不足
事業承継は経営の問題であると同時に、人間関係や感情にも深く関わるテーマです。
現経営者の「まだ手放したくない」という未練や、後継者の「本当に自分でやっていけるのか」という不安が、承継のプロセスを複雑にします。
特に親族間での承継では、家族間の感情のもつれが大きな障害となることもあります。
このように、事業承継の失敗は単一の要因ではなく、複数の問題が複雑に絡み合って起こることが多いのです。
だからこそ、早い段階から計画的に、関係者全員を巻き込んだ準備と対話を重ねていくことが、成功への近道なのです。
よくある事業承継の失敗事例
ここでは、実際に見られる事業承継の失敗パターンをご紹介します。
成功事例以上に、失敗から得られる教訓は多く、事前の準備や対策の重要性が浮き彫りになります。
後継者とのコミュニケーション不足によるトラブル
ある中小製造業では、父親が経営する会社を長男が継ぐことが決まっていました。
ところが、父はほとんど何の説明もないまま引退し、長男に社長職を丸投げ。
就任当初から社内では「何も分かっていない社長」というレッテルを貼られ、孤立し、半年後には「自信が持てない」と辞任してしまいました。
このように、承継前の準備不足とコミュニケーション不全が後継者の離脱を招くケースは非常に多いのです。
従業員や幹部の反発で組織が分裂
別の事例では、経営者が外部から若手の後継者をヘッドハンティングし、いきなり社長に据えました。
長年会社を支えてきた幹部社員たちは「外様に会社を任せるのか」と不満を募らせ、数人が退職。その後、現場の混乱が続き、顧客対応にも悪影響が出て、売上が激減しました。
このケースでは、承継前に社内への説明や意見の吸い上げ、信頼関係の構築といったプロセスが一切なされていなかったことが原因です。承継とは経営者のバトンタッチであると同時に、組織の心理的な変革期でもあります。従業員やキーパーソンの理解と協力なくして、円滑な承継はあり得ません。
M&Aによる外部承継の失敗
あるIT企業は、後継者不在のためM&Aで外部企業に譲渡しました。
しかし、買収企業の経営スタイルは成果主義を重視する合理的な体制であり、もともと穏やかな社風で「人を大事にする」文化を持っていた現場との間に軋轢が生じました。
重要な技術者が退職し、受注が減少。結局、2年後には解散という結果に終わってしまいました。
M&Aは、後継者不在の場合の有力な選択肢ですが、「いくらで売れるか」だけでなく、「どのような会社に託すか」「社員や顧客は新体制に馴染めるか」といった視点での慎重な選定が求められます。
税務対策が不十分で資産が目減り
ある企業では、株式をすべて創業者が保有しており、相続時に多額の相続税が発生。
後継者が納税資金を用意できず、会社資産や土地を売却せざるを得なくなりました。
その結果、経営権が分散し、意思決定が遅れるようになりました。
銀行や取引先からの信用も揺らぎ、資金調達にも悪影響が及びました。
税務対策は、単なる節税ではなく、「事業を守るための戦略」です。
長期的な視野で計画を立て、顧問税理士や専門家と連携して適切な準備を行うことが必要不可欠です。
いずれのケースも、もっと早く手を打っていれば避けられた失敗ばかりです。
事業承継は単なる経営者の交代ではなく、会社の未来を左右する重大なプロジェクトであることを忘れてはなりません。
事業承継を成功させるために必要な準備とは?
では、事業承継を成功させるにはどのような準備が必要なのでしょうか。単に「会社を引き継ぐ」だけでなく、組織の持続性や社員のモチベーション、取引先との関係性までを含めた包括的な視点が求められます。ここでは特に重要な4つのポイントをご紹介します。
1. 後継者の選定と育成に十分な時間をかける
事業承継の成否は、後継者の資質と準備状況によって大きく左右されます。
後継者は単に経営の知識があるだけでは務まりません。組織内での信頼、判断力、そして困難に立ち向かう覚悟が必要です。
まずは、できるだけ早い段階で候補者を見つけ、適性を見極めることが重要です。
たとえば、「親族内承継」「社内の役員・幹部から選ぶ」「外部からプロ経営者を招く」といったパターンがありますが、どの選択にもメリット・デメリットがあります。
最も大切なのは、「誰が最も会社を存続・発展させられるか」という視点です。
その後は、OJTを通じて現場経験を積ませたり、経営会議に参加させるなどして、徐々に経営の視点を養っていく必要があります。
特定のプロジェクトや新規事業の責任者としてリーダーシップを発揮させる場を設けることも効果的です。
2. 経営理念・ビジョンの共有を図る
事業承継では、「形」以上に「想い」の引き継ぎが重要です。
企業の価値観や存在意義、地域社会とのつながりといった、数値では表せない“目に見えない資産”をどう継承するかが鍵となります。
現経営者がこれまで何を大切にしてきたのか、どんな判断基準で経営してきたのかを、後継者が深く理解する必要があります。
そのうえで、自らの言葉で語れるようになれば、社内外の信頼も得やすくなります。
また、承継時には、理念やビジョンのアップデートも検討すべきです。
すべてをそのまま引き継ぐ必要はありません。
たとえば、「創業者が大切にしていた顧客第一主義」を守りつつ、「DX化や新規市場開拓」など現代的な要素を加えていくことで、理念の継承と変革の両立が可能になります。
どこを守るべきで、どこを変えていいのかを明確にしておくことは、承継後の混乱を防ぐうえでも大切です。
3. 従業員・取引先との信頼関係を築く
いくら後継者が優秀でも、組織の信頼を得られなければ、承継は成功しません。
特に中小企業では、長年勤める社員やキーパーソンとの人間関係が業績に直結することも珍しくありません。
承継前から後継者が社内に入り、現場での実務を体験することは非常に効果的です。
社員との距離が縮まり、「この人ならついていける」と思ってもらえる環境を作ることが大切です。
また、定期的に社内報やミーティングを通じてビジョンや今後の方向性を共有し、透明性のあるコミュニケーションを心がけることも信頼構築につながります。
取引先に対しても、早い段階から顔合わせや引き継ぎの場を設けましょう。「あの人がやるなら安心だ」と思ってもらえることが、承継後の取引継続のカギになります。現経営者が同行して紹介することで、信用の橋渡しがスムーズに行えます。
4. 専門家の活用と事前の税務対策
事業承継におけるもう一つの大きな障害が、「税務・法務・財務」の問題です。
特に株式や不動産など資産を多く保有している企業では、相続税や贈与税、株式評価額の問題など、複雑な課題が山積しています。
これらを自社だけで対応するのは非常に難しく、税理士、弁護士、事業承継に強いアドバイザーの力を借りることが不可欠です。
たとえば、納税資金の確保のために生命保険を活用したり、自社株の評価額を抑えるために種類株式を導入するなど、数年かけた計画が必要になります。
また、M&Aによる外部承継を検討する場合も、譲渡価格だけでなく、「どのような会社に託すか」「社員が安心して働けるか」といった視点での検討が必要です。
専門家を交えながら、適切なスキームの設計と実行を行うことで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。
事業承継は、単なる「バトンタッチ」ではなく、「未来を託す経営戦略」です。
成功の鍵は、「早く」「丁寧に」「周囲を巻き込みながら」進めることにあります。
時間と手間はかかりますが、しっかりと準備を重ねることで、会社と従業員、そして家族を守る確かな一歩となるのです。
まとめ
事業承継は、「一日で終わるイベント」ではなく、「数年単位で進めるプロセス」です。
多くの企業が、準備不足や対話不足によって承継に失敗していますが、それはあらかじめ防ぐことが可能です。
・早めの後継者選定と育成
・関係者とのコミュニケーション
・経営理念の共有
・専門家との連携
これらを丁寧に実行することで、事業承継のリスクは大きく減らせます。
過去の失敗に学び、計画的で円滑な承継を目指しましょう。
M&Aナビは、買い手となりうる企業が数多く登録されており、成約までの期間が短いことが特徴です。ぜひご活用ください。

株式会社M&Aナビ 代表取締役社長。
大手ソフトウェアベンダー、M&Aナビの前身となるM&A仲介会社を経て2021年2月より現職。後継者不在による黒字廃業ゼロを目指し、全国の金融機関 を中心にM&A支援機関と提携しながら後継者不在問題の解決に取り組む。著書に『中小企業向け 会社を守る事業承継(アルク)』
関連記事

【2025年最新】学習塾のM&Aの市場動向、買収事例や成功のポイントを徹底解説
2025年の学習塾M&A市場は、少子化と人口減少の影響を受け、中小規模塾が経営上の不安を抱える中で、多くの塾がM&Aを活用して経営基盤を強化

【2025年最新版】産業廃物業界のM&Aの市場動向、成功事例や売買戦略を徹底解説
2025年の産業廃棄物業界では、M&A(合併・買収)が非常に注目されています。 環境保護や持続可能なビジネスへの期待が高まる中で、企業は新たな成長戦略

【2025年最新版】眼科(クリニック)のM&Aの市場動向、成功事例や売買戦略を徹底解説
2025年の眼科クリニック業界では、少子高齢化や技術革新、規制の変化などの影響により、M&A(合併・買収)の動向が大きく変化しています。 この記事では

M&Aと事業承継の違いとは?それぞれの仕組みや流れ、成功のポイントを解説
>>事業の譲渡・売却について相談する 後継者不在問題が社会課題として挙げられる中で、事業承継やM&Aについて語られることが増えてきました。 この記事で
新着買収案件の情報を受けとる
M&Aナビによる厳選された買収案件をいち早くお届けいたします。





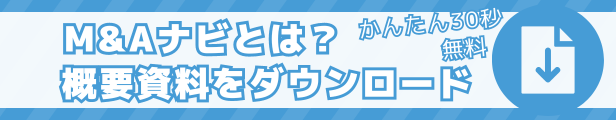





 メールで受けとる
メールで受けとる





